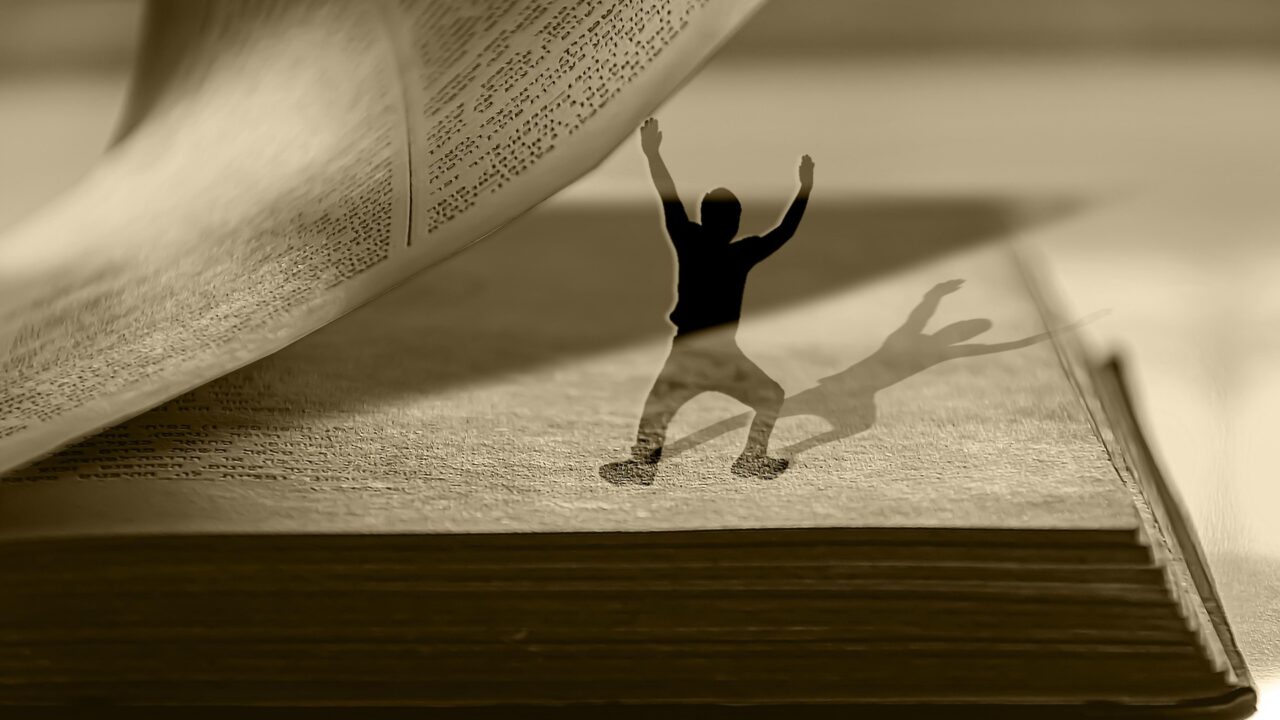ページ数も少なく隙間時間にも読める軽さながら地味にこれが一番影響が大きかったかもしれない。僕の中の「気持ちいい感じ」の結構な割合が老子の思想にあるのだと気づきました。中国思想はあまり知らないのですが、確かこれより前に『論語』を読んでみようと思ったことがありました。
でもそっちはちょっと堅苦しくて厳格な男性性の強い印象で僕にはあまり合いませんでした。一方こちらはかなり優しいです。そのせいで昨今の自己啓発本やビジネス書にありがちな「頑張らない生き方」の枠組みに取り込まれてるのもよく見かけます。
でも僕が思う老子の思想はそういうことでもなくて、いや、まあそういうことでもあるんですけども、頑張る・頑張らない、ではなくとにかく「自然であること」というイメージなんですね。「水が高いところから低いところに流れるように生きる、振舞う」というくだりが非常にしっくり来てます。
あとは対極にあるものの二項対立ではなくて、振り子みたいに一番端っこに行ったときはもうすでに逆側の始まりである、という世界観も、ぴったりはまりました。
僕は曖昧さが苦手で、というか基本的には人間はそうだと思ってるんですが、白か黒かはっきりしてないと気持ち悪いです。だから答えが出てないものに取り組むのは気持ちが乗らないし、意味とかルールとかの全体像がつかめてないと動きたくならないものだと思います。
ノウハウコレクター的になるときはだいたいこういう感覚です。絶対的な正解か答えがあると思っていて、これは正解なんですか、不正解なんですか、どっちなんですか、ということにこだわりたくなる。
でも2極のどちらかしか知ろうとしない、そこにとどまり続けようとする、というのはおもしろくないんですね。その中間の微妙なところに面白みがあって、今の気分やシチュエーションでちょうどいいところに調整するのが、心地よい今日を生きるということなんだと思います。
柔軟性とも言えるかもしれませんが、両端で固まりすぎていると、間の面白いところがすり抜けていきます。
『暇と退屈の倫理学』についても書こうと思っていましたが、その著者の『中動態の世界 意志と責任の考古学』という本があって、当時すごく気になっていました。それはもう完全に「中動態」というフレーズで。今見てきたこととすごく近そうです。まさに間ですよね。
これについては結局読めてないので、実際の中身は分からないんですが、この間の感覚について書かれてるはずだと思いました。「箱から出る」という話を前回書きましたが、その時の「今いる世界の淵に立つ」というのは、主体的に壁際まで行くが、最後に外に出る瞬間は受け身的に訪れます。
僕にとってはこの主体的と受動的のちょうどいいハイブリットが「中動態」だと勝手に思っています。実際の本は読めていないので、それとは関係なしに「中動態」というフレーズを見て思ったのがそんなイメージでした。
老子の思想の好きな部分と非常に近いです。
近いついでに言うと、『タオ自然学』という本で、東洋思想と現代物理の関連性について書かれていて、たまたま僕は物理科の学生だったので、その内容がすごくしっくり来ました。
老子で出てくるタオ(道)は、そこから万物が生まれてまたそこに帰っていくようなものとされているんですが、物理で言えばこれは素粒子が生成消滅を繰り返す「真空」という場に対応するわけです。
ノーベル賞を受賞した物理学者の湯川秀樹は、その着想を『荘子』から得たと言われています。湯川秀樹の著作集は大学の図書館でいろいろ読んだのですが、漢文の素読を子供の頃によくやっていたと書いていました。
『非属の才能』を書いた漫画家の山田玲司のYouTubeをいくつか見たりもしたのですが、そこで老荘思想を語ってる回があるんですね。僕はこの『非属の才能』もちょうどそういうやりたいことが分からない時期に読んだのですが、それがこの老荘思想を語る人だとは知りませんでした。
本を買うのとこのYouTubeを見るのは、時間もメディア空間も全然違う地点で起きた出来事なんですが、どちらも同じ人でした。
ということを見ていくと、僕が好きなことや好きな感覚にはたいてい、老荘または老子ニュアンスが含まれているんだとわかってきました。その原点はこの薄い漫画本でした。
好きなもの同士のつながりやその源流をたどってみると、そこに共通するものとして、自分にとっての「気持ちいい感じ、好きな感じ、やりたい感じ」が出てくるのかもしれません。
◀やりたいことが分からない読書録2『天然知能』郡司ペギオ幸夫
▶やりたいことが分からない読書録4『大人はもっと遊びなさい 仕事と人生を変えるオフタイムの過ごし方』成毛眞
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の補足音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。