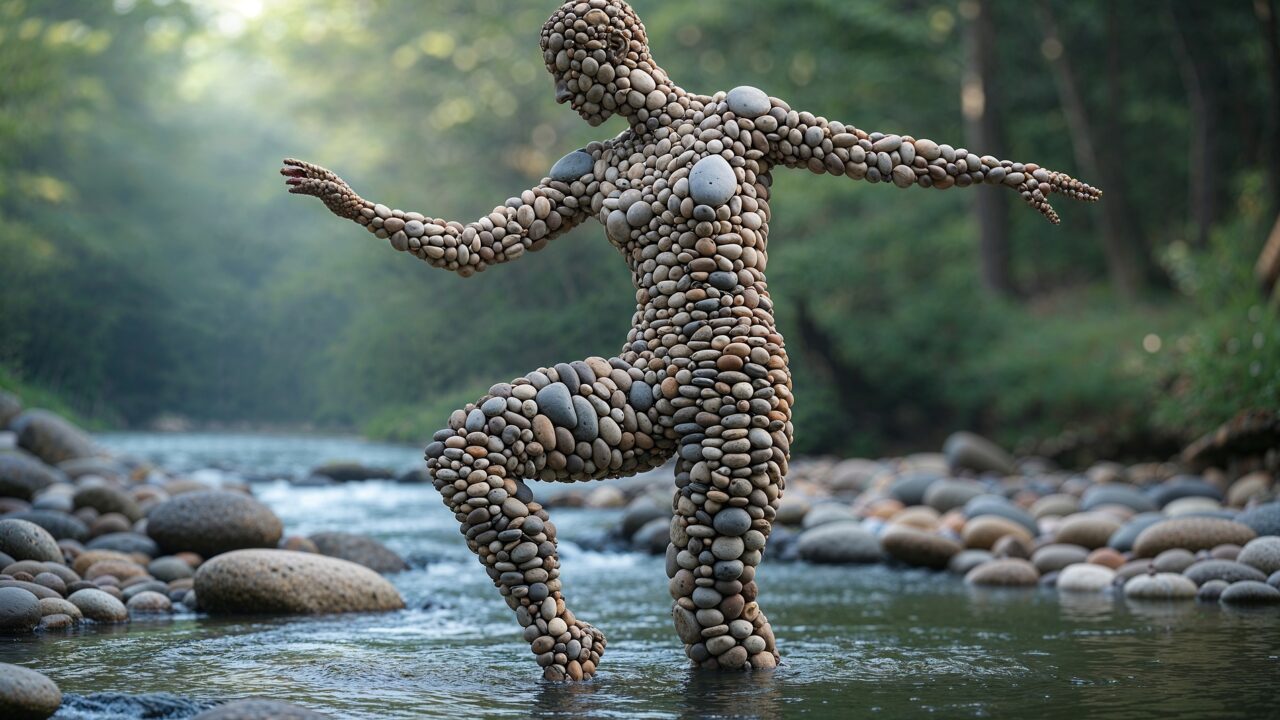最近、鶴見俊輔の『限界芸術論』という本を読んでいまして。
こんなことが書いてあったんですね。
「なぜ、教養もあり閑もある後代の日本の名称たちが、無学無名の貧しい朝鮮の陶工以上の作品をつくれないのか? この問題が、柳の美学の中心的な課題となり、この問題についての柳の解答がその後の民芸運動を支える理念となる」
柳宗悦が民芸とか、物や道具の美しさに関心をもってこんなことをして~、みたいなくだりなんですが、今回取り上げたいのは内容ではなくて、
この「問いから運動に発展していく流れ」がめっちゃおもろい、というか美しい。
問いから運動へ
ある活動でも概念でも物でも何でもいいが、「それらはどんな問いに対する回答なのか」という視点で見るのは面白い。
例えば、アップルの製品は、ジョブズの「情熱を持った人間は世界をよりよく変えていける、そしてクリエイティビティこそが人類を前進させる」という信念と、「じゃあそのために自分たちは何ができるのか」という問いに対する答えとして生まれてきたもので(スピーチ動画)、
フェイスブックもマークザッカーバーグが「all people want to connect(人はつながりたい生き物である)」と考えたことから生まれたサービスであり、
その他、宮沢賢治の農学校や吉田松陰の松下村塾などもそういう問いから生まれてきていると考えれば、「それはどんな疑問やフラストレーションに対する解決策として誕生したのか」という視点である対象を掘り下げることができる。
それはその本質をつかみ取る上では重要で、そこが文脈を作る。安易に言えばストーリーともいえるし、大枠を掴もうとするときの足掛かりともいえる、
変な解釈をしないためにも重要で、例えば、近代科学や哲学のことでもいいが、そういったものを考えていく時に、「それらは何をどう変えようとして生まれたものなのか」という視点は必要になってくる。
▶科学と変な付き合い方をしないためにその源流を含んだ哲学史を見ていくという話
現状は問いに対する自分の回答の現れ
逆に、読み取るばかりではなく、自分が生み出すことを考えても、それは別に何か世界を一新するサービスや革命的な概念ではなくても、「自分はいま生活する中で何を疑問に感じ何をどうしようとしてどんなことをしているのか」、と考えてみることもできる。
具体的な話で言えば、やることが多くて整理出来ないときは、todoとかタスク管理という分野になると思うが、そのときには、「今、何が疑問なのかどこにフラストレーションがあるのか」、
ただタスクを管理できればいいわけではなく、タスク管理と言ったときには、その日にやるべきことがちゃんとなされる状態がいいのかもしれないし、もう少し広げてみれば、何をやって何をやらないかを判断する軸が不足しているのかもしれないし、仮にそのタスクが全部できたところで満たされない何かがあるのかもしれない、
だから、どんな疑問や違和感のもとその行動になっているのか、つまりここでは「何故、タスク管理が気になっているのか」「なぜ会社に行ってるのか」「なぜ大学にってるのか」「なぜその分野を専攻しているのか」、
現状というのは、その疑問に対する今の自分の見解の現れであって(仮にそれが「なんとなく」であったとしても)、今の生活という答えを変えるには回答へのアプローチを変える必要があり、その答えを考える過程が、自分の文脈で物事を探求していくということで、
それは自分の方法を作るともいえて、そしてその答えがまず抽象的な、概念的なものとして頭の中に立ち上がり、そのある種の理念とかスローガンともいえるものを反映するかのように動き実行することで、実際の生活の方が変わっていく。
自己治療、他者の薬、社会とのコミュニケーションとして
この時の理念やスローガンはそれが人生全体をカバーするとき人生の軸と言えるが、そうではなくても日常のある領域に対しての疑問とそれに対する回答、またその反映としてのアクションという形で現実空間のあらゆる物質や活動は存在している。
そしてこれは自分の治療のために物事を考えているともいえるが、そうやって導き出された答えやそこから生まれる製品サービスは誰かにとっての薬ともなり、その形で社会とも接続していく、
逆に、周りの人間が何にフラストレーションを感じているのか、そのために自分はどういうアプローチをとることができるのか、という答えとして生まれるものもあり、ブログの記事などはそのようなプロセスをたどることが多い、
特に日記やエッセイのようなものではない、コンテンツと呼ばれるようなものは、「誰かが誰かの疑問や問いに対する答えを言語や音や映像に変換したもの」である。
つまり、何らかの対象についてそれがどんな問いから生まれたのか考えることは、
その本質を外さず掴み取る上でも、自己の問題を解決する具体的なアクションや活動につなぐうえでも、周囲の人間の苦痛を和らげるサービスや製品を生み出すうえでも、それによって社会とコミュニケーションを図る上でも重要な営みと言える。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。