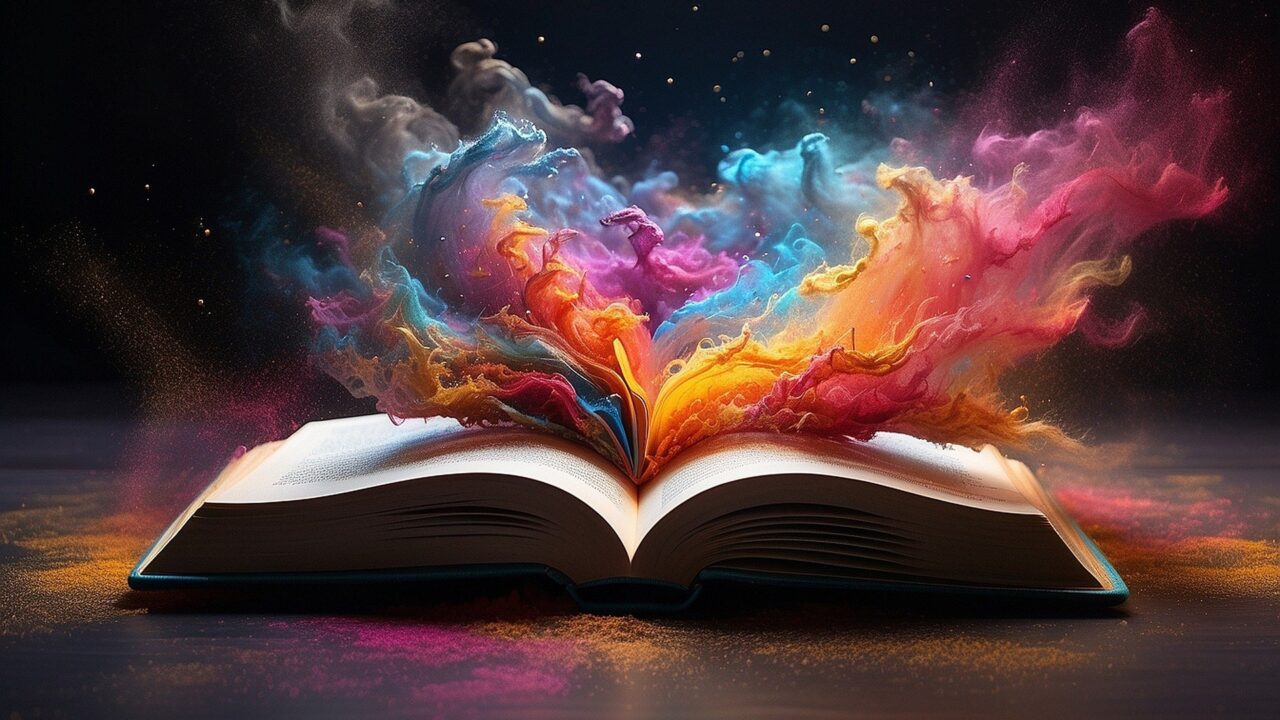こんにちは高本です。
今日は「その背景が分かるから理解が深まりより楽しめるようになる」という話です。
ちょっと前に、「物理学史」という授業が物理科のカリキュラムにあったほうがいいんじゃないかと思ったんですね。
その前にまず歴史というものについてちょっと考えておきましょう。
歴史を学ぶ意義と面白さ
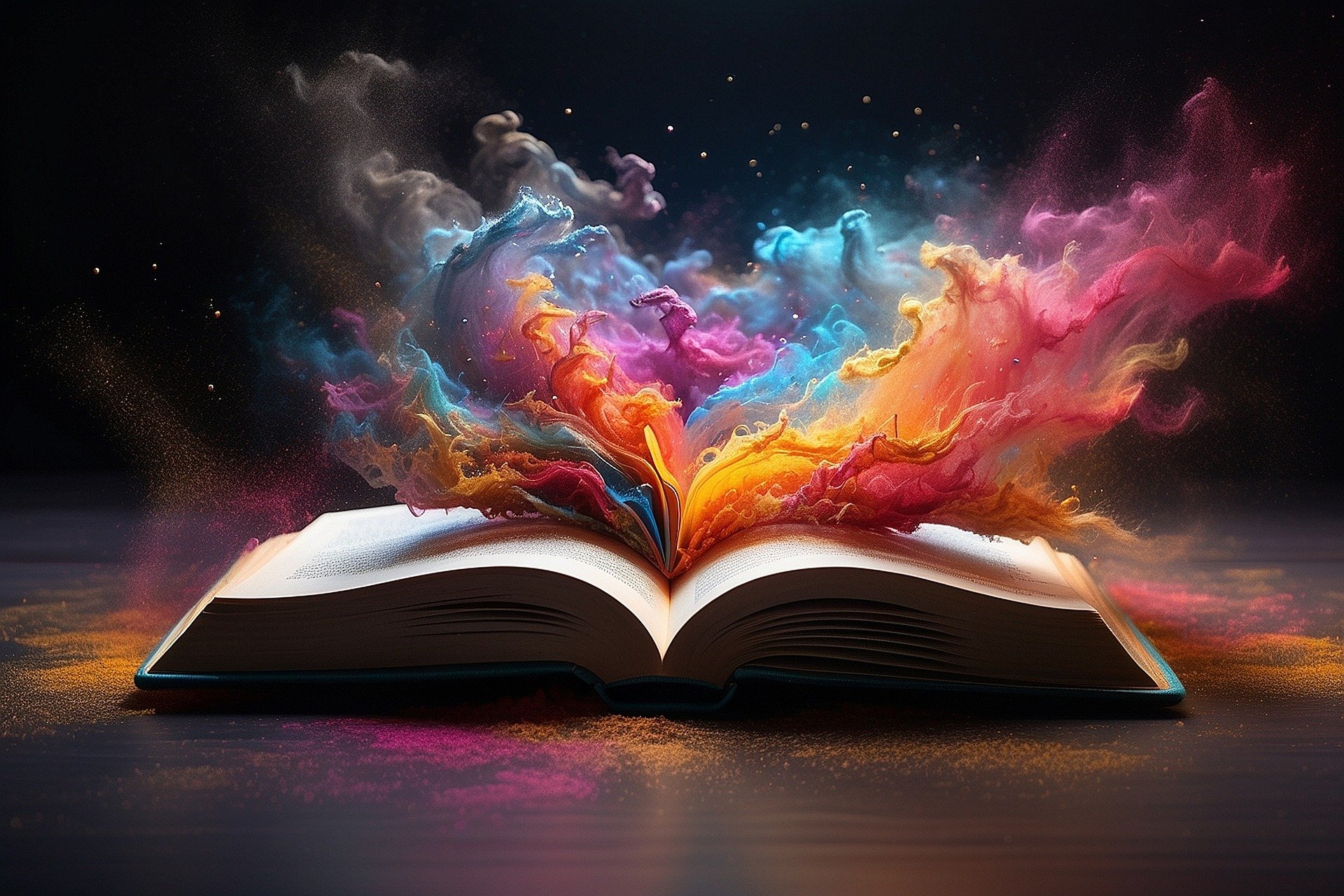 僕は何か学ぶ時に歴史がすごく大事だと思ってるんですね。
僕は何か学ぶ時に歴史がすごく大事だと思ってるんですね。
歴史と言えば社会が思い浮かぶと思いますが、学校でやるのは大体日本史と世界史ですよね。
でも歴史というのはすべてのものにあるわけですね。
今、身の回りにあるものはすべて始まりがあって、そこからの時間の流れがあります。
それが歴史ですよね。始まりから今に至るまでの物語が歴史ということです。
そうすると、何か主張とか命題があったときに、それにも歴史があります。
そのときの社会があって、その人が置かれた状況があって、そこでどう動いた、考えたことで、それが生まれた、という時間の流れがあるわけです。
何か商品でも意見でも常識でも。
で、僕たちが今知ってる目の前のその事実とか主張とか結論というのは、その前の歴史を知ってこそだと思ってるんですね。
つまり、一番ケツの部分、英語で言うと、the latest の部分だけ知ってても仕方がないというか、本当に芯から味わうには至らない。
例えば、名言とかも、どんな社会をどんな風に生きた人がどんなタイミングで言ったかというのが分かってないと響かないはずです。
たしかに、それを知らなくても名前も込みでぐっとくることはあるかもしれません。
でも名前も結局、その人が生きた歴史を僕たちが漠然とでも知ってるから響くわけですね。
量子力学の歴史を知らず教科書で説明されても難しすぎる理由
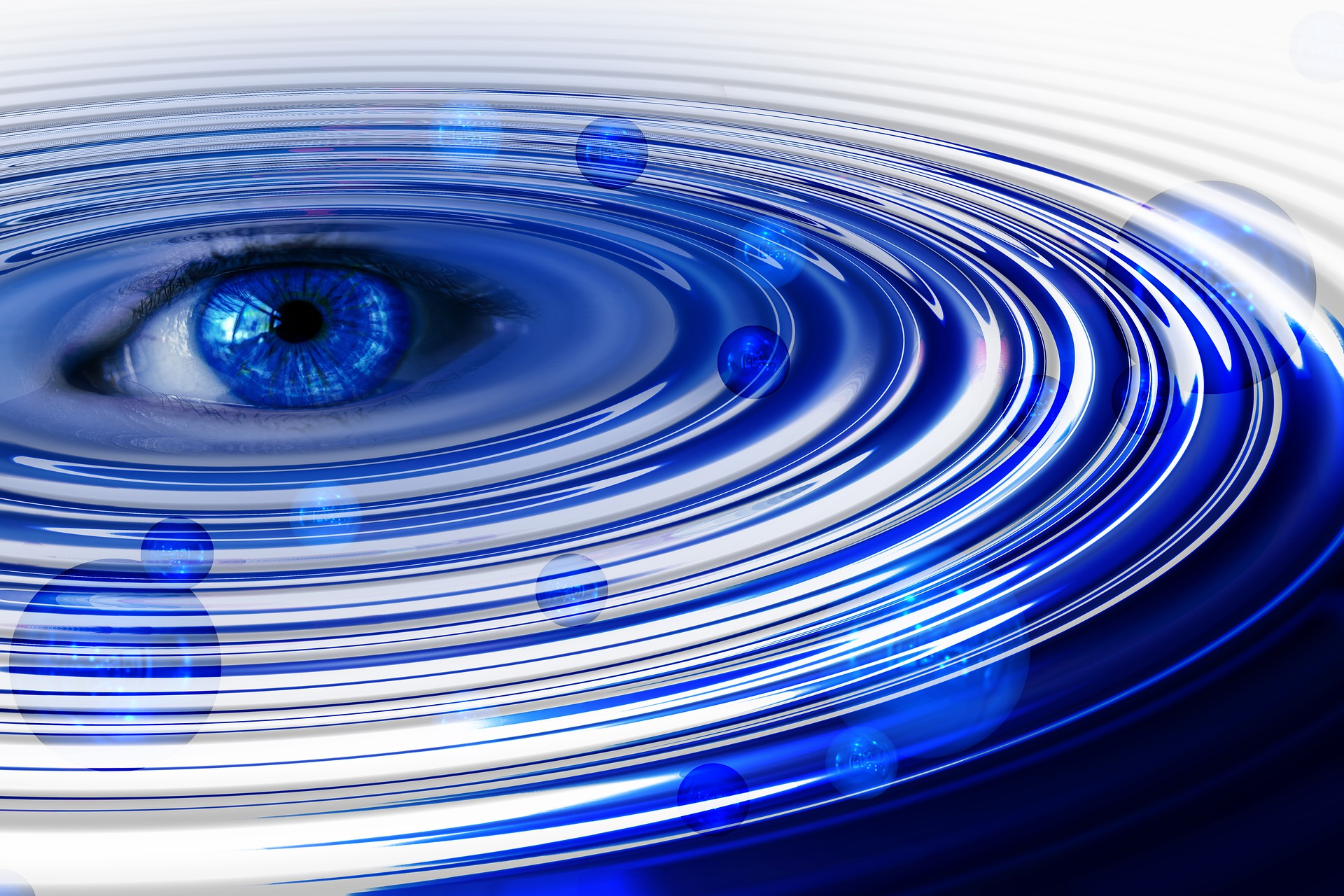 で、これは勉強でもそうだと思ったことがあるのです。
で、これは勉強でもそうだと思ったことがあるのです。
僕は大学は物理学科だったので、確か2年生から量子力学をやるんですね。量子力学というのは、その当時の物理の世界の常識に反することだらけです。
だからまじでわけがわかりません。
で、それを余計にわからなくさせてるのは、もう理論が整備されて整いまくった教科書を頭から進めるからなんですね。
教科書はもうある程度量子力学が出来上がってから、それをうまく順番に説明できるように書かれてるわけです。
でも本当はそこにも歴史があります。
これまでの物理では説明できない現象が見つかってから、それを扱える理論を作ろうと多くの理論物理学者が何年もかけて試行錯誤してきた歴史があるわけです。
それを順番に見ていけば、「まず現象として不思議なことが起きた」というのは受け入れたうえで、
「最初はそれをどう説明しようとしたのか」
「そして何がうまくいかなかったのか」
「じゃあ次に誰がどうしようとしたのか」
という流れで進んでいけます。
で、そうやって見ていくと、教科書で急に表れた謎の概念とかが、なんでそれが必要だったのかというからくりが分かります。
もちろんそれは教科書や授業でも触れられはしますが、事細かにやってる暇はありません。
「じゃあ自分でそういう本を読めばいいやん」という話なんですが、そのときにはそうやって「歴史をたどれば意外とわかる」ということを知らないわけです。
イントロに知ってる概念が出てくるまで遡っていくっていく形で論文を読む
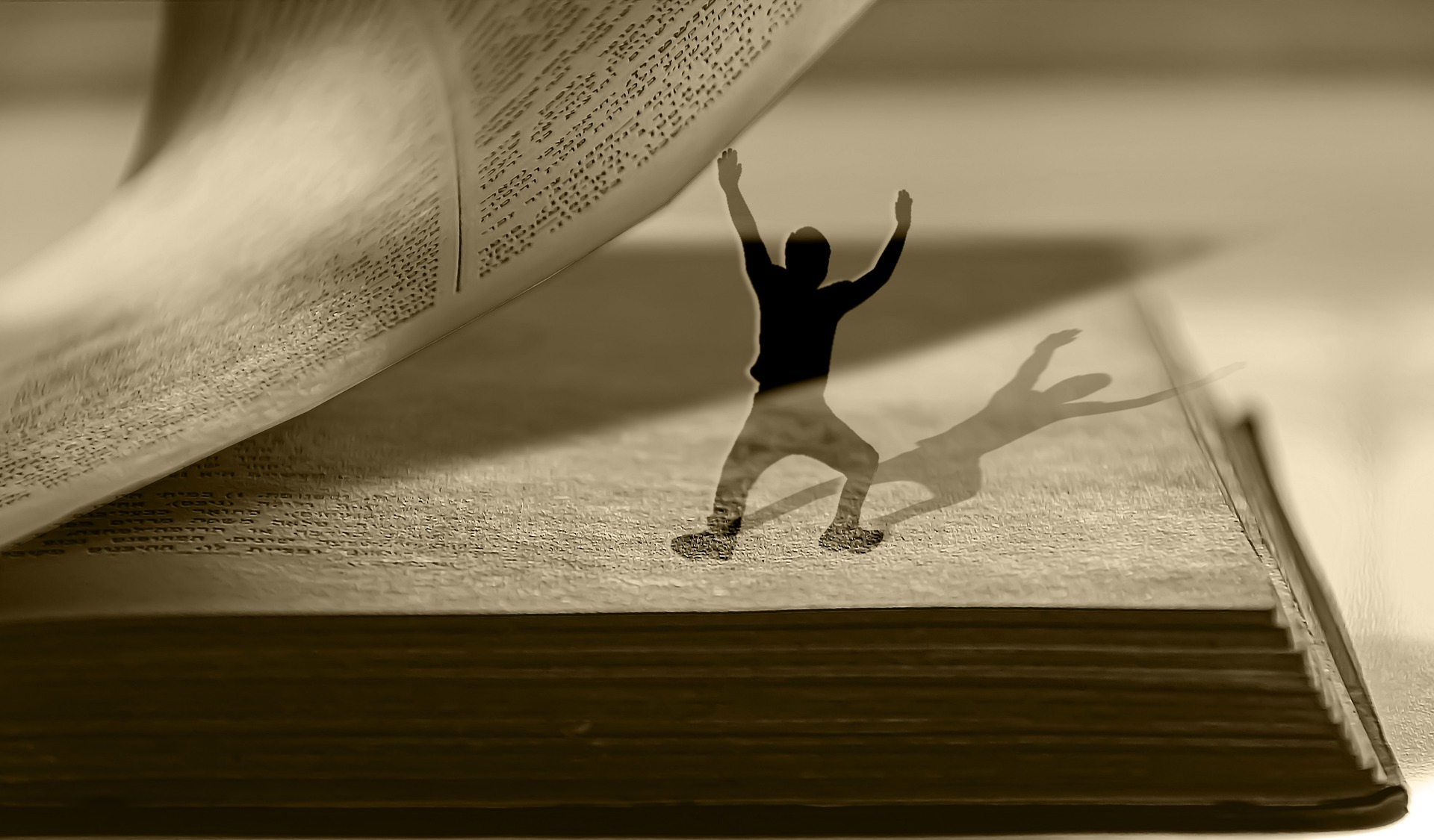 僕は大学院生になって研究テーマを探すときに、自分が興味ある分野の最新の論文を見てみたんですね。
僕は大学院生になって研究テーマを探すときに、自分が興味ある分野の最新の論文を見てみたんですね。
そうすると、まあ全く分かりません。「これは何をしてるねん」と。
で、論文のイントロの部分を見ると、「どういう経緯でこの論文が書かれてるか」ということが書いてます。
でもそのイントロもわけわからないんですね。そうなると、次はそのイントロで触れられてる論文に遡ります。
でもまだ分かりません。
じゃあもう一つ遡るわけです。
そうやって数十年分遡っていくと、途中でやっと「聞いたことある話出てきたな」ってなるんですね。
そうすると、とりあえず今やってることと、その中間地点までの距離感は分かります。
で、あとはそこを埋めていくように勉強するんですけど、それがめっちゃおもろいんですね。
というのは、それって、「問題点が一つずつ解消されていく歴史」なんですね。
「今ここまで理解できているとされている」
「でもここはちょっと問題がある」
「じゃあ次の人がそれをこんな形で説明してみた」
みたいな感じ。
ブラックホールで言えば、最初は一番シンプルなブラックホールを考えるわけです。
で、じゃあ次は電気を帯びてるやつで考えてみたらどうなる。回転してる場合はどうなる。違う次元だったらどうなる。
って進んでいきます。
そうすると、最新の方の論文を見ても全く分からなかったはずが、数か月たって見返してみると、「あーだからここでこの話出てきてるんや」ってなるんですね。
もっと言えば、教科書とか授業でもう当たり前のものとして進んでたことすら、元の論文があります。
そこで「さすがにここまでは常識としていいですよね」ってなったから教科書にまとめられてるわけですね。
そうすると、そこまでが一つの歴史として認識できるんですね。
教科書ではわからなくても、先人たちの試行錯誤ごと捉えられるようになる。
そうすると理解の仕方が全く違ってきますよね。
同じ結論でも、その後ろでこちらがイメージできている情報量が桁違いなので。使いこなし方の自由自在度が全然違うわけですね。
まとめ
これはちょっともう細かい話なんで何となく見てもらったらいいんですが、量子力学って「どこにその粒子が存在するか」を確率で表現するんですね。
まずそれが謎なんですが、それにも理由があります。ここではやらないですが。
で、それを「確率振幅」という概念を使ってなんやかんやするんですね。
これは、「二乗するとその電子が存在する確率に関係する値が出てくる」というものなんですね。
で、意味わからないじゃないですかw何のためにそんなものを導入して何を頑張ろうとしてるのかと。
というのを、量子力学の授業の一発目でいきなり説明されたんですね。
実際はもうちょっと丁寧に喋ってくれてたかもしれませんが、でも僕たちからしてみればそんな話は入ってこないのです。
で、結局だいぶ先まで進んで、「あーだからそんな話を最初にしてたのか」とわかるんですが、
それは量子力学の歴史を知れば、自然な物語として分かるんですね。
しかも、そこの試行錯誤の部分がおもろいのです。
これは、レポートでも書いたんですが、「工夫」だからですね。
「試行錯誤+結果」というストーリーは、僕たちがそれを使って将来をシミュレーションできるために、面白く感じるようになってるんです。
というわけで、収拾がつかなくなりましたが、「その背景が分かるから理解が深まりより楽しめるようになるという話」でした。
ぜひ、物語や歴史の部分で遊んでみてください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。