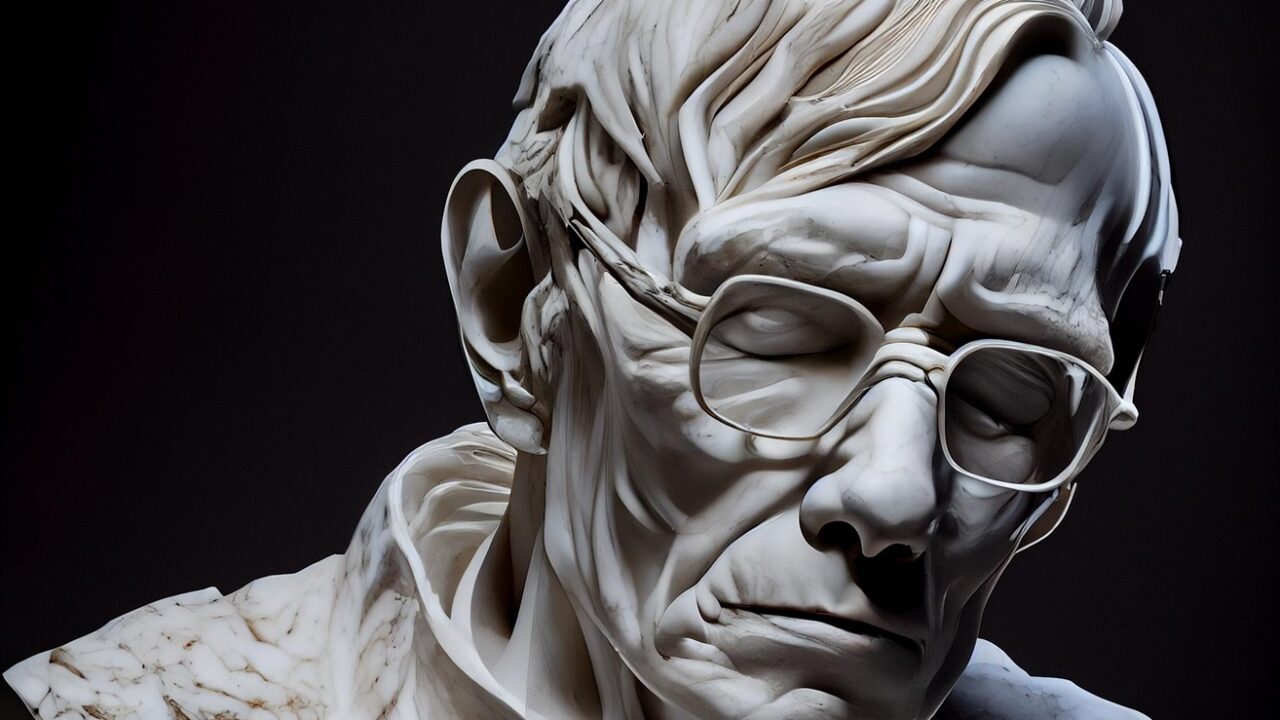平山夢明というホラー作家の「恐怖の構造」という本を見つけた。ハンターハンターの富樫義弘がストーリーの勉強をするときに参考にした作家として筒井康隆と平山夢明を挙げていて、その時に知った。レビューに、」本人は研究者や学者ではないので自身の経験や好きな作品から考察されている」って書いてた。学者ではない人がある概念や対象の本質を掘り下げていくという現象というか状態について少し考えてみたい。
この問題はよく出てきて、個人が一つのテーマについてひたすら考えたことと、またそれとは別にアカデミックの世界で広く認められている通説があったとして、それらを僕たちは第三者としてどう受け止めればいいのか。めっちゃ簡単に言えば、その個人の経験や思考からくる仮説を正しいステップを踏んで研究されたものではないからとすぐに否定するのは違うくて、でもかといってそれはどこまで行ってもその人が考えたことだから、盲目的に信じるものでもない。
もう一つはちゃんと研究されたものだからと言って、そっちだけを学んでも実生活に落とし込めないと意味がないわけです。意味がないというのは、その研究はそれ自体に価値がありますが、その論文をもとに自分が今取り組んでることに応用させるにはそのままでは使えはしない、ということです。
冒頭の恐怖の話で言えば、小説を書くとして、そこで読者に恐怖を感じてもらいたいと思ったとして、心理学や脳科学では恐怖はどう捉えられていてどこまで解明されているのか、分かったとして、でも今の目的は読者が恐怖を感じる小説を書くことです。だから最後はそこに落とし込まないとこの文脈においては目的を果たしなことにはならない。
でも逆に今なら個人の経験や実際に何を考えてどうやってるのか、という話は分かりやすく役立てやすい可能性があります。実際にある作家がこんな風に考えてこういう仕掛けや構成をとっています、という話は応用しやすい。これは一人の人間が実際にやってることという具体性があるからですよね。論文やそういった研究は個人の目の前のアクションとは距離が遠いということが今わかりました。
この両方を考えていくのが難しくて、でもどっちも同じことを言ってることもあるわけです。学問として正しいステップを踏んで証明されたわけではないが、個人が自分の体験をもとに考えたことが結論としては同じになることがあって、つまり、物理で明らかになったことがそれよりもっと前に仏教の本に書いてたりするわけで、同じ山を別のルートから登ってるってことだと思うんですね。というか、階層が違うだけって感じなんですかね。
例えば、『野生の思考』では未開部族も科学という形ではないだけで、自らの経験をもとに、同じような答えを出してるわけですよね、まあちゃんと読んでないので具体的なことは分からないんですが、ざっくり言えば、その植物を食べていいかどうかを成分を分析しなくても、経験的に茎の部分を見れば食べれるか判断できると知ってる、みたいなことでしょうか。
で、そういう具体的な知識が、後から研究していけば、実際に茎の部分に人間にとって有害な成分が含まれてるかを判別できるヒントが現れてることが明らかになったりするってことですよね。恐怖の構造という本を見つけてそんなことを思ったんですね。
これは昔から思ってたんですが、例えばブログだと最初にその記事でどんな話をするかを書きなさい、みたいなことが言われてたりします。で、それは経験的に納得できるわけですが、人間の注意や認知を掘り下げてみたときに、全体像をつかんでると我慢できるみたいなことが分かってたりするのだと思います。信号があと何秒で切り替わるか分かってれば耐えられるみたいな話と関係してるのかもしれません。
で、じゃあ冒頭にそういうことを書けと言われて、それをやってるだけだとどこまで行っても人のまねで誰かがやってたことを後追いでやるだけになります。かといって、勝手に学問として人間のことを掘り下げていっても、この場合ならブログのその記事を見てもらえるというところに繋がってないと、繋げられないと当初の目的は達成できてないことになります。
他で言うと昔のプロ野球選手が死ぬほど素振りして身につけたフォームが、最先端の人体構造について理論から導かれる、その人にマッチしたフォームの要素を全部満たしてたりすることがあります。これも個人の経験と学問的帰結が重なる瞬間です。これはどう考えたらいいんでしょう。
個人がある行動や思考を突き詰めていくとそういう理論とつながるってことですかね、ってなると今度は逆にじゃあその科学というものをどう考えればいいのかということにもなってくるわけで、つまり、一人が考えに考えたことが科学的に明らかになってることと同じであれば、「よっしゃ正解にたどり着いた」ってそんなことでいいのかってことで、いいわけないんですが、じゃあ何がよくないのか、というか科学や学問との距離感をどう思っておけばいいのかって問題になってきます。
さっきのに話を戻せば、例えば、誰かが自分の生活の中で考えたことや試したこと積み重ねたことは、その領域に限っては研究で明らかになってることとはあり得るわけで、というかあり得るも何もその人がそれによって満足したり欲しい結果を出しているのであれば、その人にとってはそれが正解で、その、「その人にとっての正解」も元の研究はふくんでいないとおかしいことになるわけですよね。
自然科学で言えば、というか物理で言えば、全てその法則で説明できる、というものが正しいとして認められます。ニュートンの世界観で、物質の運動をすべて説明できていたからそれで数百年何とかなっていました。でももっとミクロな世界ではそれに合わない現象が出てきた。ってことは、ニュートンの世界観からはみ出た世界がこの世界にはまだあったってことですよね。それでもある領域に関してはその世界観で包み込むことができていると。
で、これをもう少し考えてみると、ニュートン力学の世界の時にもすでにそこからはみ出ていた現象はあったはずですよね。でもそれは当時の常識からははみ出てるからそっちが間違ってるということで無視されるわけです。もっと言えば、物理の世界に限らず、個人の生きてる世界においてはそんなことが起きててもおかしくないです。
それが仏教とか禅で言われてるような話ですよね。そっちではもう先に、今の世界観では答えを出せない命題が知られていて、もしくはそんな問題を考えようとしていて、誰かがまたはある集団が頭をフルに働かせていった結果、この世界はこういう風になってるはずである、という答えのようなものが出たと。でもそれはニュートン力学の世界にはマッチしてません、
でも3百年後ぐらいに量子力学の体系が出来上がっていく時に、やっぱりあってたやん、ってなったりするわけですよね。そうすると個人の体験を突き詰める中で出てきた仮説や答えが今の常識から外れるとき、それはまだ科学で明らかに出来ない領域であるだけ、ということが考えられます。
そもそも今の常識というのは、それよりもっと昔に誰かが研究してその界隈で間違ってなさそうだと認められたから無事に成立してるもので、教科書に載ってるのもそういうことですよね。でも歴史で言えば、また新たな説が出てきて覆されたりする。例えば坂本龍馬なら僕たちのイメージする坂本龍馬は教科書で紹介されるようなそんなイメージであるはずです。
さっきのブログの話で言えば、じゃあ仮に冒頭にその記事の概要を書くことが常識になってるとして、それはもっと前に誰かが人間の注意力に関する研究をもとに自分のブログに当てはめ、それで一定の成果が出たらから、それをやる人が多くなり、ブログはそういう風に書かないとだめですよって言いだす人が現れ、その一連の歴史を知らない人は、ブログを始めるときにそういうものか、と思って常識として受け入れることになるわけです。
で、それはがダメということではなく、それで結果が出てることを感じた人がいるから受け入れられてるわけですよね。でもそれが唯一の階ではないってことなんだと思います。それは科学で明らかになったことを自分のブログという目の前の活動に当てはめたときにうまく言ったやり方、または誰かが自分の問題として試行錯誤を重ね徹底的に考えていったときに、さらに自分の経験とも当てはめてこういうやり方がいいんじゃないかと導き出されたやり方であるだけで、それ以外の方法がダメということにはならない。
むしろまだ誰もやってないやり方を試し、それがうまくいき、他の人はたまたまやろって感じていたが、それが五年後研究結果として明らかになりました、ということは余裕であるわけですよね。
ただ、ここで注意する必要があるのは、徹底的に考える必要があり、誰もやってないという時に、全員が試して意味なかったからやめたものって可能性もあるということです。だからその意味では本当に慎重になることが求められますが、今の常識の外にあることをその時点で排除するのはそれはそれで危険です。
そもそも個人の経験や具体的な現象が先にあって研究することになるわけです。つまり、自分たちが気づけるすべての現象や、仮設のうち、多くは間違っていて、だからみんなが認めている範囲にとどまろうとしてしまうが、そのうちいくつかは今後明らかになる、まだみんなが見落としているものってことは十分にあるわけですよね。
だから科学とか学問とはどういうものなのか、という性質をちゃんと自分なりにわかっておきたいってことになってくると思うのです。
▶科学と変な向き合い方をしないためにその源流を含んだ哲学史を見ていくのが大事ですよね、という考え方が面白い
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。