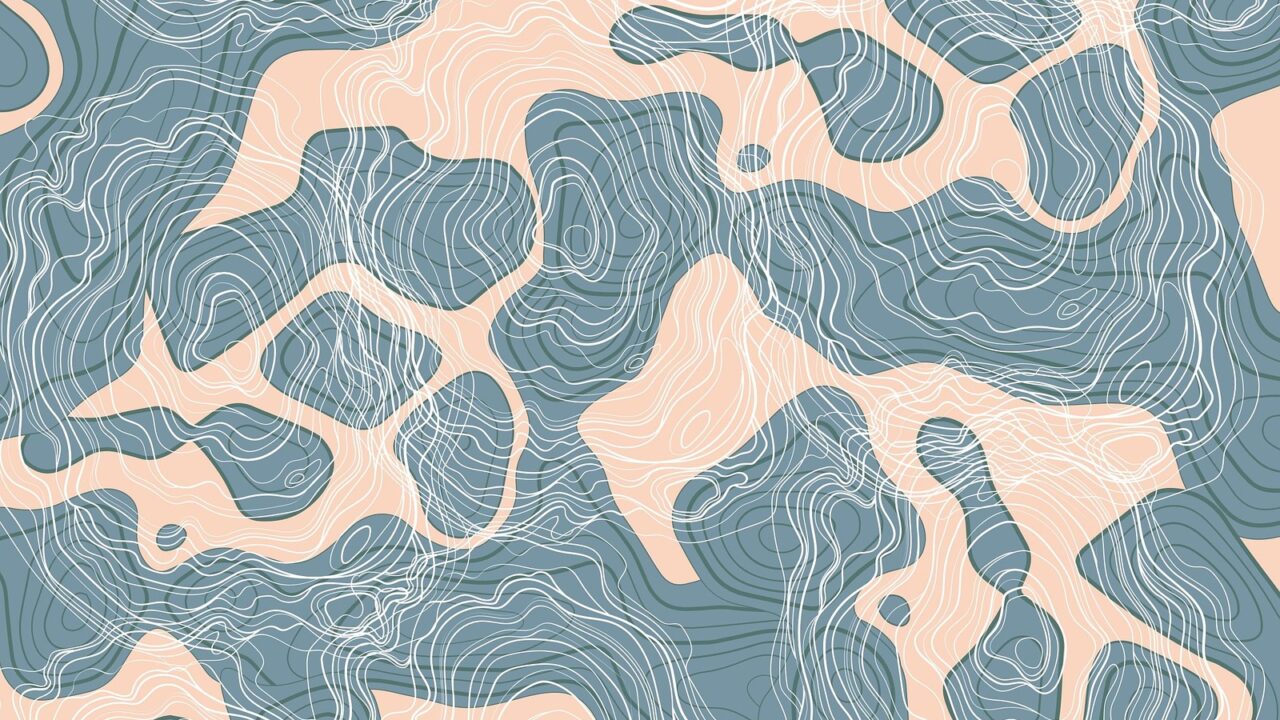最近ちょこちょこ鶴見俊輔の「限界芸術」の話をする割にあまりちゃんと説明されたものがなかった気がしていたんですが、
前にLINEで配信したものにちょうどいいのがあったのでそれをこちらで共有しておきます。
今度から限界芸術の話が出てきたら本を読むかここをサーッと見てもらえればいいということにしよう。
限界芸術についてはこの辺で出てきてた。
▶非専門家は枝分かれに気づかないからこそ全体のまま受け取ることができるという話
芸術で灰色の労働を燃やす
こんにちは、高本です。
今日はJTA通信の第7号を配信しようと思ってたのですが、ちょっと間に合わなかったので一回飛ばしましてw、
今回はこちらで少し芸術と僕たちの生活がどう重なっていくのか、何を読み取っていくのかという話をしたいと思います。
前回、シクロフスキーの「異化」という概念を考えていました。
彼によると芸術作品は、
「普段馴染みありすぎて自動化になってスルーしてしまうところに引っ掛かりを生み出し、ゆっくりとした知覚を起こし、生の感覚を取り戻させてくれるものである」
という話でした。
で、そこで次に見てみたいのが宮沢賢治の言う「農民芸術」で、これはネットで見れるのでぜひ見てもらいたいんですが、めちゃめちゃ熱い話をしてます。
「今は宗教や芸術が科学技術にとってかわられ、でもそれらは冷たい。
上の世代は楽しそうに過ごしてたけど、今はただ生存や労働のみになっている。
だから新しく自分たちの芸術を作って行こや、
『芸術をもてあの灰色の労働を燃せ』」
というわけです。
で、じゃあその芸術ってなんやねん、というとこれは、「農民の日常生活から起こってくる芸術」です。
日常生活から立ち上がってくる非専門家による芸術
例えば宮沢賢治は、農学校の生徒と修学旅行に行けばそこで詩を書いたりしてるわけですね。
脚本を書いてみんなで劇をしたり、農学生の日記風の短編を書いたり。
「誰人もみな芸術家たる感受をなせ」と。
つまり、「非専門家による芸術」で、これは鶴見俊輔の言う「限界芸術」です。
専門家による純粋芸術でもなく、ドラマや映画などの大衆芸術でもなく、非専門家による芸術作品。
普通は、美術館に行くよりも、夕陽や町並みを見るとかによる美的な経験が大半なわけですよね。
だからそこに着目していくのが『限界芸術論』なんですが、ここで民芸運動の提唱者、柳宗悦の話が出てきます。
世界の新しい美しさを発見し示していく、という姿勢
彼は「日本の伝統に自信を持ちその目で世界を見ることで、世界の新しい美しさを発見して示していこう」とすすめます。
これが面白くて、つまり、この人は日本古来の工芸や民芸に関心をもって、わびさびなどの日本的美学によって世界の新たな姿を見つけて示していこうとしたわけですが、
もう少し広げてみれば、人それぞれ異なる感性というのは「だから自分はこれを楽しむ」で終わらずに、
そこから「世界の新しい美しさ、他の人が気付いていない面白さに気づき、それを周囲に広げていく段階」があるということです。
さらに、この「今いる日常的な状況から芸術が創造されていく」というのは、哲学者の三木清が「実証精神」として、
「学問は今の暮らしの中から生まれてこなければならない」
と言ってたのにも通じてきます。(小林秀雄特集の回参照)
「生活」を媒介にして学問と芸術をつなぐ
そうなると、学問と芸術は「生活」を介して同じレイヤーの上で議論も実践もできることになります。
つまりどちらも、
今ある状況、文脈、弱さ、好きな感覚、価値観によって新たな形で世界を捉え、
そこに現れた風景や概念の面白さ、美しさ、すばらしさを周囲と共有していくという社会とのコミュニケーションの形がある。
▶そこにこだわらざるを得ない弱さが創作や探求のエネルギーになるという話
これが、エネルギーの源泉を特定してその方向に掘り下げ開拓していき、そこでゲットしたものを循環させていく、という話ですよね。
ちょっと死ぬほど抽象的になってしまってるんですが、今回は「人生ちゃんと遊ぶという観点での芸術の解釈のさわり」をお送りしました。
ありがとうございました、それでは!
↑まで引用
というわけで、かなりおおざっぱでしかもいくつかの話題に流れてはしまってますが、なんとなく限界芸術のイメージは出来るのかなと思います。
僕は特に芸術とか文学とか興味ないというか自分には関係ないと思ってしっかり健康に生きてきたんですが、
見方によってはこうやって文章を書いてることにも芸術的側面は純分にあって、もっと言えば専門家ではない人はこういった形で日常的に芸術に触れているわけです。
触れていたり自分自身が生み出していたり、極端に言えば適当な鼻歌すらも芸術なので。
そう考えたときに、普段の生活から起こってくる美的な経験や感覚、ここについて考えてきた人の話はちゃんと聞いておくのも悪くない。
その文脈に鶴見俊輔と「限界芸術」という概念があり、さらにさかのぼれば宮沢賢治の農民芸術もその系譜で、さらに宮沢賢治が参考にしたところにウィリアムモリスがいて、日本で言えば民芸運動を巻き起こしていく柳宗悦がいます。
彼らの思想に当たりつつ、日常から何かが生み出されていく感覚を洗練させていきやしょうという話でございました。
ちなみに、一番最後の件の「開拓から循環~」については↓のPDFで大枠の話はしてます。
▼開拓して循環していく話

現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。