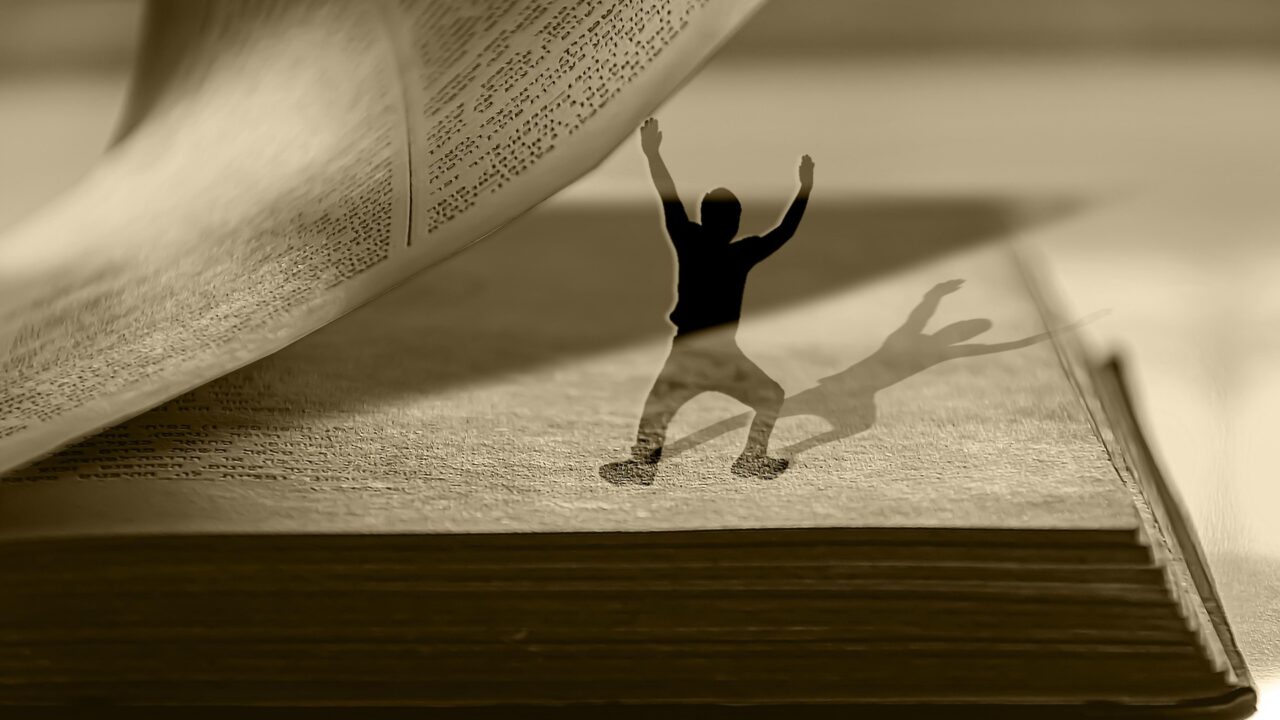作家の森博嗣が夢を叶えることについて語ってる本なんですが、かなり印象に残っていて何度か読み返した記憶があります。そもそもこの人の考え方が好きで、小説は一冊も読んだことないんですが、エッセイ本はいろいろ読みました。『なにものにもこだわらない』とか『自分探しと楽しさについて』とかも面白いです。
何がいいのかというと、完全に独断と偏見なんですが、この人は良く言えば素直でまっすぐで、悪く言えばひねくれてるのです。だから自己啓発本感あるタイトルでありながら中身を見てみると、そういう本の逆側から攻めてくるわけです。
夢と言っておきながら現実的な今日のアクションにフォーカスした話も色々あって、とにかくコンスタントに作っていくというくだりがあります。確か毎日一時間しか執筆しないらしいのですが、十分で千文字を六セットぐらいやるらしいんですね。
で、合間に鉄道を作ったりいくつかの趣味を織り交ぜながら、でも毎日淡々と仕事を進めていく。村上春樹は毎日四千文字書くという話を聞いたことがあります。抽象的な将来の漠然とした絵を浮かべるのではなくて、凝り固まった今日をとにかくまず動かす、そんな次の一手が浮かんでくるような本だったと思います。
別の本なんですが、「ときどき、自分は何を作り出しているか、と考えてみよう」という見出しがあって、これは今でもたまに思い出すぐらいのインパクトがありました。
やりたいことがあるとかないとか考えてるときって本とかネットとかで大量にインプットすることになりがちで、で、もちろんそんなことも分かっていて、だから「行動力が~」みたいな言説に触れることもあるんですが、でもそれを見てるその瞬間もインプットの時間なので、結局受け取るばっかりになっていて、だから不健康で、でもそれももちろんわかっていて、ただどうやってアウトプットすればいいか分からない、みたいになりがちなんですが、だから何を作り出しているか、と言われると、当然何も作ってないわけですね。
で、何を作ればいいか分からないからこうして本を読んでいるのだ、と思うんですが、そこで何かを作るという時のハードルを上げ過ぎていることが問題だったのです。別に歌でも絵でも文章でもアクセサリーでも何でも今面白そうに感じたことを作ってみればそれで一歩前進するのですが、それの何の意味があるのかと思ってしまいます。
でも、じゃあ逆に自分にとって意味あるとはどういうことか分かってるのか、という話で、それが分からないから困ってるわけですが、今の自分が意味あると思ってることしかやろうとしない姿勢が現状を生み出してるわけなので、とりあえず今、今日面白そうに感じたことはすべてやってみればよかったんですね。
この本を読むと、自分が夢とかやりたいこととか人生の方向とか言ってることがいかに適当かということを思い知らされます。人生のテーマとか目標とか言っておきながら考えが甘すぎるわけです。甘いというか、手前過ぎるというか、具体性が無さ過ぎるというか。
例えばお金が欲しいのであれば、なぜお金が欲しいのかということですよね。じゃあ仮にきょう百万円もらったとして、今から何しようか考え始めるのだとすれば、別にそんなに必要としてませんよね。
めっちゃ具体的に誰とどこでどんな風にどんな生活をしたい、って思えば、消去法的に今どうしているべきかどういうやり方があるか見えてくるんですね、たぶん。
例えば小説家になりたいとしたら、自分にとって小説家になってるとはどういうことかって考えられるわけで。実は考えてみたら、一日何時間書く時間が欲しいとか、自分が書いたものを誰かに読んでもらいたいとか、お金が欲しかっただけとか、別に今広く使われてる言葉としての「小説家」という言い方をしなくてもよかった可能性もありますし、そうなればその生活ができる形を探すという現実的な具体的な行動に変換されます。夢っていうのはそうやって考えるんですよ、みたいな話が押しつけがましくない形で書かれていました。
◀やりたいことが分からない読書録7『流れをつかむ技術』桜井章一
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。