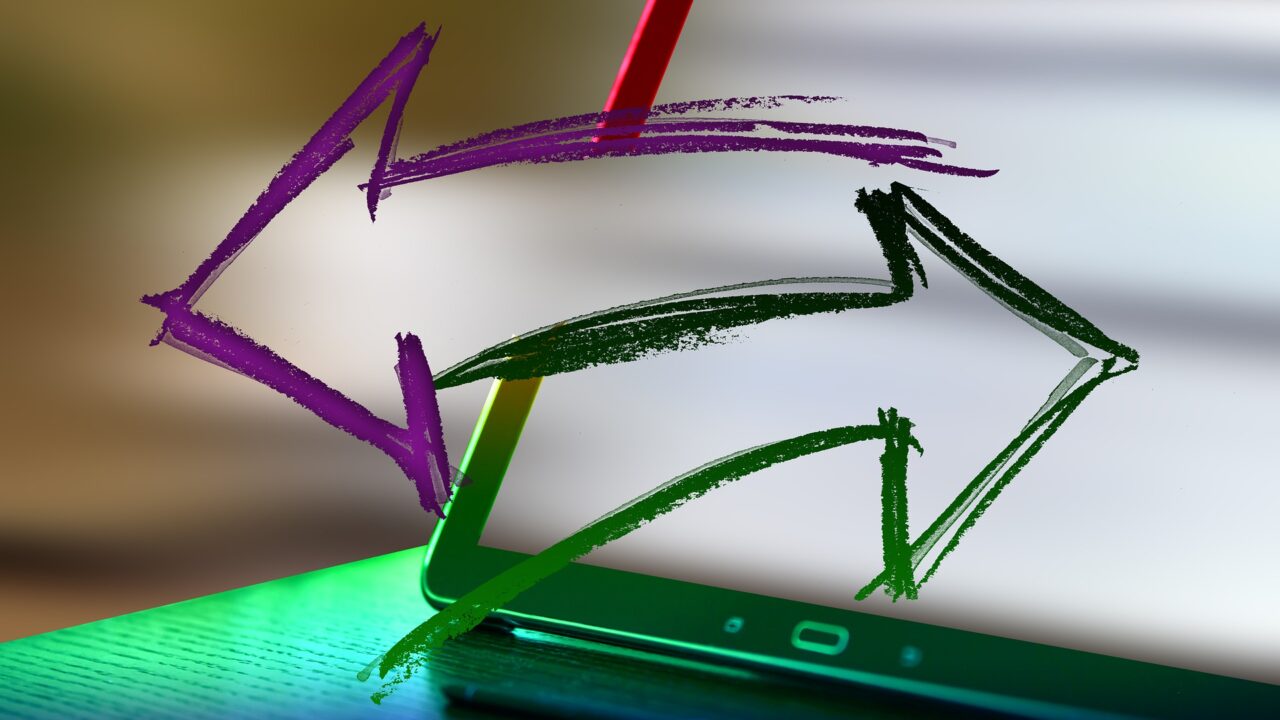少し前に経験と意味の関係や対応が気になっていた。
経験というのは人と話したり自然に触れたり楽器を演奏するような感覚器官を通した入力で、意味はそれらに対する解釈の事。
経験と解釈の偏りとバランス
ここで、例えば家で本を読むというのは、そこに書かれている概念やロジックによってそれまでに経験した出来事にラベルを張りつけることになったりするので、意味付けの方に対応している。
すごくあっさい例で言うと、心理学の本に返報性の話が出てきて、「確かに誕生日プレゼント貰ったら自分も返すなあ」と思えば、それまでの、もしくはそれ以降も似たような場面で「これは返報性が働いている」という形で出来事に対する解釈が行われるかもしれない。
ちょっと例えとして返報性はダサすぎるというか、何かもらったり上げたりして返報性が~とかいちいちそんなこと考えてるのはきしょいって話ではありますが、何となくすっと共有できそうな例で浮かんでしまったので仕方がないとして、
でもこっちの側に偏ると、少数の(またはその時点までの)自分の実感のある臨場感のある出来事や体験や感情のみをもとにその意味を整理していくことになる。
これは本を読むのは自分の考えを強めることでしかない、というもので、だから外に出ろ、人と話せ、新しいことに挑戦しろ、とよく言われる。
一方で外でのそういった経験は、一瞬の考えを湧き上がらせるが、それはある強度を持った意味付けとはすぐにはならない、だからそれを踏まえて自分で考えて整理していくことになり、その時に本が読まれる。
それは似たようなテーマや問題は各時代ごとにどのような考えてこられたのかを知ることができ、その全体を総合的に考慮してその人間によるその経験の意味付けがなされる。
だからこの経験というのはいわばフィールドワークで体を通したデータ、物理の実験では客観的なデータが室内でとられるのに対して、ここでの経験は個人の身体を通した感覚器官を通過し脳に届く入力のことで、このデータをもとに個人がある体系を形作っていく。
離れた地点に経験を並べ土台とする
この時、意味付けや体系化ばかりになればわずかな体験というデータの上に膨大な意味が乗っかることになり、地に足がついていない、または個人に閉じたものになりかねない。
あるカテゴリーある領域、ある単一のラベルの狭い範囲での経験の身の上に築かれた意味は不安定であり、だから離れた地点に土台を作っていきたい、ということになる。
この時、じゃあその経験の強度はどうなのか。
一番簡単な例としては、新しく草野球を始めてみますというとき、どれぐらいやってればいいのか。
それはもう一つ上の前提、つまり何のためにそんなことをしたいのか、そんなことというのは草野球ではなく、離れた地点に経験を増やしそれらに意味付けをして体系化や編成をしていく動機で、それはその方がおもろそうやんとしか言いようがない。
遠く離れた経験の上に意味を乗せその意味の上にまた経験を重ねそのピラミッドを高く積み上げることでしか見ることのできない上からの眺めが最高でしょう、ということのみ。
この時に枠組みや論理がポイントになってきて、その経験はただ一つあるだけだが、枠や論理を持つことで、
それらのいくつかの経験と自分をセットで同時に扱うことができ、どこに位置しているのか知ることができ、体験または思考の穴や漏れに気づく、それは次に目指したい方向となる。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。