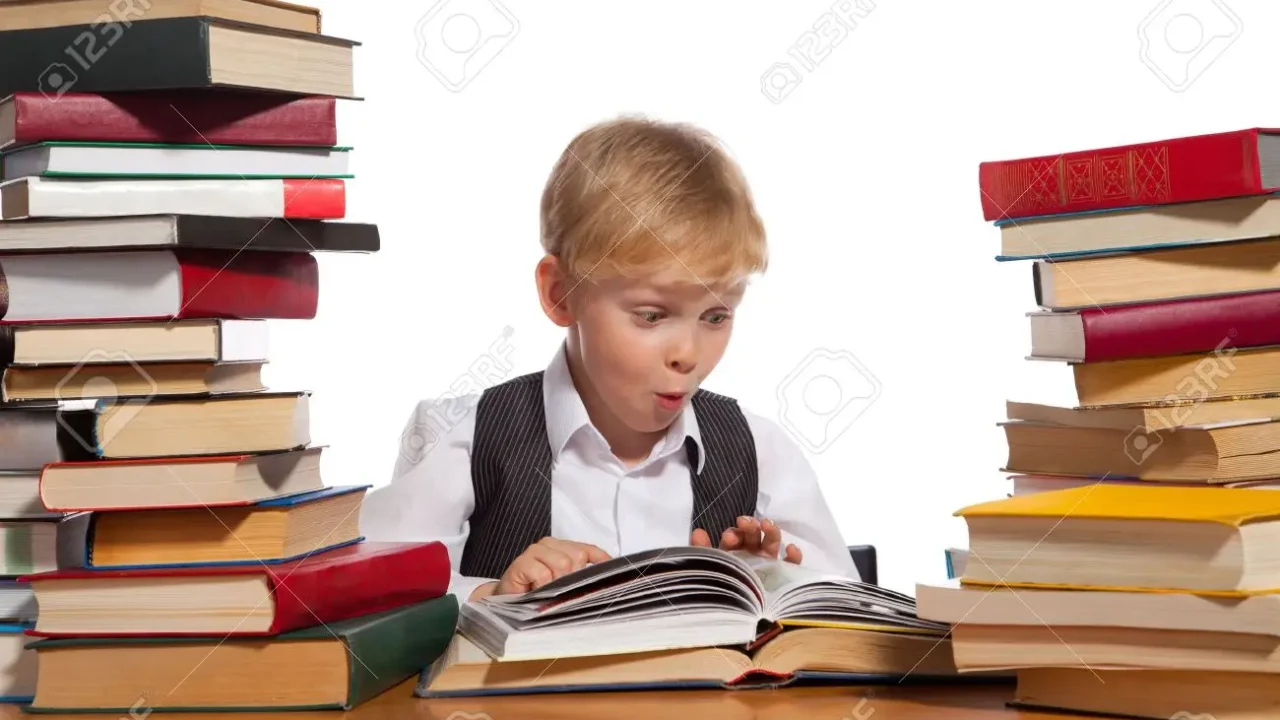最近読んで面白かった本たちの雑なメモ。
気になったところだけ簡単に抜粋していきます。
①少しだけ無理をして生きる/城山三郎
経済小説の作家みたいですが、これはエッセイっぽい感じでこっちのほうが好き。
ざっくり「人の魅力とは」っていうのが軸になってそうな本。
伊藤整さんも、「新人賞の選考会では、一橋の後輩のあなたに何もしてやれなかったけども、一つだけ忠告をするよ」と言ってくれました。
「あなたはこれから先、プロの作家としてやっていくのだから、いつも自分を少しだけ無理な状態の中に置くようにしなさい」
少し無理をする、少し負荷がかかる環境を作る。
この辺は非常に大事な感覚ですね。
もうひとつ。
中山素平という銀行家がいます。私も尊敬している人物ですが、彼がよく口にする言葉に、「箱からでなくちゃいけない」というのがあります。中山さんが人を評価する基準は、「あいつは箱の中に入って安住しているか、それとも箱から出ようとしているか」という点なのです。最初にお話ししたように、安住しないことは初心を忘れないことでもあります。
自分がいる箱の中に安住してしまってはダメで、自分がその中にいる箱から出ていこうと、チャレンジし続けなくてはならない。
枠から抜け出す、箱の外に出るっていうのはこのブログでも何回か出てきてると思います。
現状維持は衰退っていう言葉もあるぐらいなので、やっぱりこういう姿勢でいたいところです。
②私の嫌いな10の人びと/中島義道
この人が嫌いな人たちを書いた本。
なんとなく世間的にいい人に思われてそうな人を、片っ端から嫌いと言ってるのですんごい逆張り。
何個か挙げてみると、
・笑顔の絶えない人
・自分の仕事に「誇り」をもっている人
・常に感謝の気持ちを忘れない人
・「けじめ」を大切にする人
などなど。
こういう人を嫌いとおっしゃられております。
”専門バカと普通のバカ”っていう見出しにある文章が印象に残ってます。
一芸に秀でた人、特にそれによって社会的に成功した人は、一芸に秀でるために、人間として必要なさまざまな訓練を怠ってきたたことを認めなければならない。人間としては、いびつでほとんど奇形に近く、そのことを恥じなければならない。それなのに、単にテニスができるだけの男が、単に料理がうまいだけの男が、単なる落語家が、単なる漫画家が、テレビに登場してきて、人生万端とうとうと意見を述べる。こういう鈍感な輩が大嫌いということです。
僕は大学で多少成績よかろうが、その内輪の言葉でしかコミュニケーションできなかったらなんも意味ないやんと思った時がありました。大学2年生ぐらいのとき。
▶狭いコミュニティに長くいると、その外にいる人間と会話出来なくなるという話
それで地元の友達だったりいろんなコミュニティの人と関わるように変えたりしていったので、結構刺さります。
これに近いようなことを感じてたのかなあと。
ほかにもいろいろ鋭いことを言ってるので面白いですw
③ライフワークの思想/外山滋比古
人生の折り返し地点に来たらどっしり構えて何か一つじっくりやってみませんか。
みたいなニュアンスの本。
3章以降はイギリスのパブリックスクールとか特に興味のない話なので、2章まで。
で、この本ではカクテルとアルコールの対比が前半によく出てきました。
・カクテルはもともとあるものを混ぜるだけ
・原料は自分の頭で作り出したものではない
・酒だから酔いはする
・でも一滴たりともアルコールを作ったことにはならない
こんな流れがあったうえで、次の文章が印象に残りました。
ビールを作るには麦が必要だ。どんなに醸造の経験があっても、麦がなければビールはできない。人生の酒に必要なのは経験である。この経験を本土を読んで代用したのでは、カクテルになってしまう。やはり、その人が毎日生きて積んだ経験というものを土台にしなければならない。そして、それに加えるに経験を超越した形而上の考え方、つまりアイデア、思い付きをもってする。経験と思い付きとを一緒にし、これに時間を加える。この時間なしには酒はできない。
これはめちゃくちゃいいこと言ってると思いますw
やっぱり自分の経験が土台にないとだめだと。
哲学をかじったような人が薄っぺらく感じるのは、本で読んだことをそのまましゃべってるからですよね。ベースの実体験の部分がないから。
そういえば別の本の中で、
「知恵は実生活に根差しているけど知識は机上のもの」
とも言ってた気がしますがそれも同じことですよね。
やっぱり自分の五感というフィルターを通って入ってきたことを、最も大事に扱っていくということになりますね。
最近で気になった本たちでした。
ではまた。