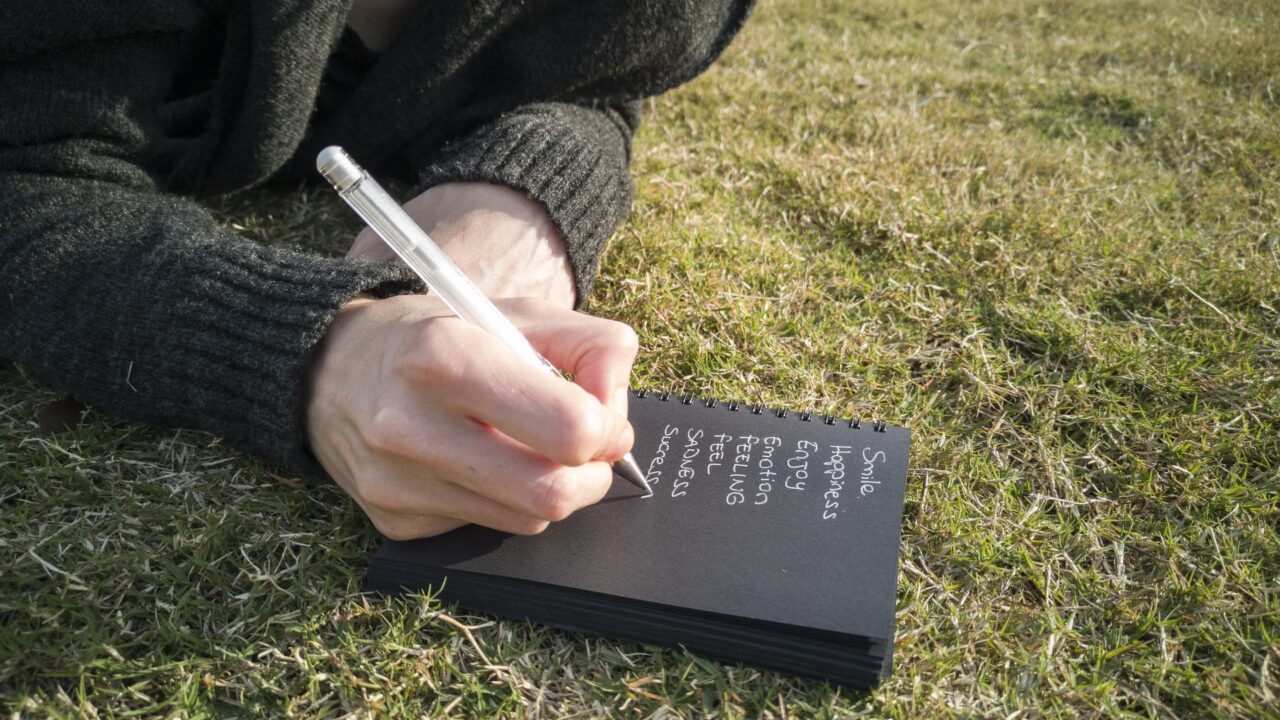やっぱり毎日書く必要がある。
一日の中で本を読んだり考えたり文章を書いたりできる時間には限りがあって、16時間起きているからと言って16時間使うことはできない、
それどころかこういう頭を使う系のことはできても5時間ぐらいで、そうすると本を読むのが増えると当然書く時間は少なくなり、
で、この時の書く時間というのはその読んだ本についてのメモとは別種のもの。
いわゆる読書メモとか、何らかの気付きをちょっとメモしておこうという時のメモは断片で、それが人に向けて書かれるというか、人が見ることのできる形で書かれるにしても読み物ではない、
読みものと言えるのはある分量を伴った流れのある塊のことで、そしてこの読み物としての形で書かれる中でしか出てこない言葉があり、それはもう少し具体的に言えば、
一定の時間、いま頭に浮かんでいる何か、見えている光景、感じている流れを捉えようとする間にしか出てこない言葉の連なりがあり、それが考えるということで、
そうやって考えることで初めて掴み取ることのできるぼんやりとした概念というものがあり、そこに次のテーマや進むべき方向がある。
で、この時これがただ自分のために書かれたものではあまり効果がなく、それは「人に向けて」というのは、「将来また読むことになる自分に向けて」も含んでおり、
この時の自分が読み返して意味が通じない可能性がある文は論理的な流れが成立していないわけで、それでは日常を過ごしている中では掴み取れない深い部分を掘り起こすことにはならない。
フリーライティングとも違う
ただ適当に書くことはよくフリーライティングと言われるが、これはどっちかと言えば、これによって何らかのアイデアや概念や今の興味関心の種を見つけ、それをさらに考え掘り下げよう、という試みであり、
それと異なるのは「そうやって書かれた文章それ自体が一つの読み物としてそこに出来上がる」ことを念頭に置いて書き始める。
これが人に向けて書くということであるが、この時の人というのは特定の誰か、つまり自分以外の読者というのともまた少し違っている。
どっちかと言えばさっきも書いたようにまた次に読む自分に向けてという意味合いが強いかもしれない。
そうなると、ここで、そんな文章は非常に狭いというか、個人に閉じたものになるような気がしてくるが、これもまた意外とそうではなく、
あらゆる概念や思考やエネルギーが織り交ぜになった頭の中を、一本の流れとして線として、外に出してくる行為が書くということであって、
そうやって生れ出てきた線というか塊を、近い未来の自分や自分ではない誰かと一緒に覗き見るというだけである。
この時、個人に閉じた狭いつまらない文章というのは、その人間が考えていることが閉じた狭いつまらないものであるということ。つまらないのはそいつの頭の中であって、手法の話ではない。
脳内のカオスを成形する
そして人間の思考というのはもちろんいつでもきれいに整っているわけではなく、むしろそっちの方が自然で、
例えば会話のように人に向けて話される段階になって、その都度一つの流れとして取り出されるもので、
だからこそそうやって日々書いていくことは、このカオスを認識可能な形に成形するということであり、これが生活のリズムを作る。
というのは、いくつか理由があり、まずはそれが広く言えば一つの生活から生まれる芸術であると言えること。
書かれたものがその人間が生きた痕跡
もう一つはこうやって書かれることで今の自分が何に関心があり何を問題視していてどう進もうとしているのか、最新の現状把握ができる、
さらに、そうやって日々書かれたものはログとなり、それ自体がその人間が生きていることを示す痕跡となる、むしろそれこそが自分にとっても他社にとっても自己紹介となる。
また、人の興味や考えていることは常に更新されているもので、後からまとめよう整えよう、というのは基本的には難しい。
それはまず時間の話で考えれば、今の興味に向かう時間と、少し前に進んできた道を整えるという二つの時間が必要になり、その分だけ、頭を動かすエネルギーが必要になる。
物理的な時間というエネルギーと、消費カロリーというエネルギーの二重で負担になる。
また、終わった話を整理するのはシンプルに今の興味ではないのでだいたい面白くない。
そういうわけで、毎日毎日考えていることを書きかいて考えることが、その一日のリズムを作る。
書くことによって自身の現在地が分かり次に進もうとしている場所が分かり、何を知りたいのか何をやりたいのか何を考えているのかわかり、そしてその個人とは、そうやって連続的に書かれたもの全体のことである。
P.S.
いやこのブログは毎日更新されてませんやん、と言われかねないので大いに先回りして言い訳しておくと、書くことは毎日やりたいしやっているが、更新作業は毎日やりたくないのです。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。