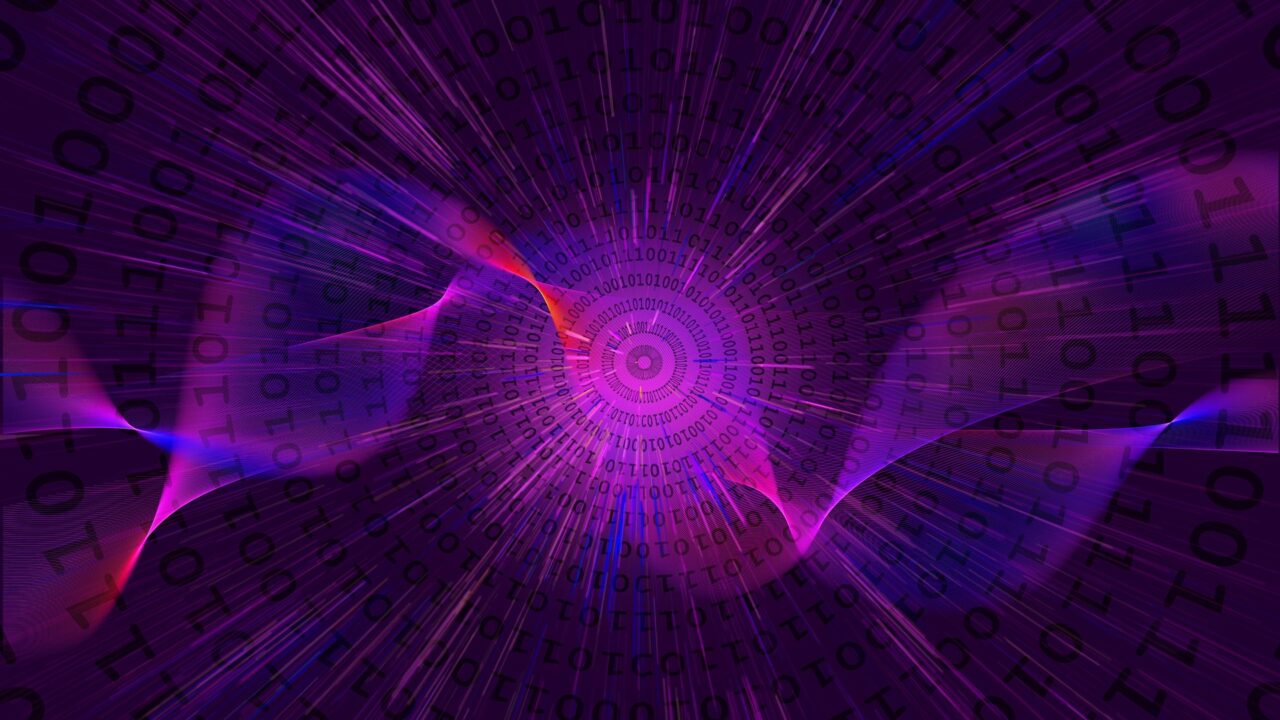論理を更新していくことについての話を何度かしてきたので、ここでの論理の具体例を考えてみる。
▶「ものを認識する論理、それ自体について考えておこう」という感覚がめっちゃ面白い話
▶「自分・世界・その間にあるもの」を別々に考えるのではなく全部をまとめて扱える論理を探求していきたいという話
座標系という論理
論理というのは、例えばある場所を認識する場合にxyが直交した二次元平面で解釈しようとすれば、(3,4)の点は「x軸方向の単位ベクトル3個とy軸方向の単位ベクトル4個分」という形で表現して解釈することになる。
ただ、これは二次元の直交座標を採用したからであって、斜交座標という斜めに交差した座標系のシートをかぶせて認識しようと思えば、斜めの単位ベクトルを使うことになる。
つまり、その場所を認識するとき、「自分はその静的な対象を客観的に認識した、これは固定的で変化なくちゃんと認識できてる」と思いがちだが、
それが直交座標の上で認識していたのだとすれば、それは「あくまでもその宇宙、その言語の世界の認識」に過ぎない、
例えば、その場所を指さして「あそこ!」って言うことも出来て、これは日本語で認識したわけだが、これだとさっきよりはあいまいになるわけで、
だからどの言語とかそれにより形作られるどんな論理の世界での認識なのかということはかなり重要で、というか、そこに大きく左右される。
今のはあるポイントを表現するだけだから単純だが、他で言えば、
ある粒子を認識するときにそれをニュートン力学的に認識するならただのボールだが、量子力学的には微妙に振動していることになる、
それはつまり、そのニュートン力学や量子力学という宇宙、そこでの言語、方程式で捉えたときに認識の仕方が変わるということ、観測者とその粒子の間の関係が変わる。
対象が人生の場合の論理
これもただの粒子の理解だから「ニュートン力学的認識なのか量子力学的認識なのか」というだけで、もちろん違いは大きいが、とはいえ「その二択のどっちでの認識なのか」というだけだが、
ここで、その対象がもっと複雑な、例えば「人生」とかだとすれば、これはどっちの論理でも捉えることは難しい。
となったときに、そこで、
「人生という対象」と「自分という主体」との関係を考える論理として適切なのは何か
ということになる。
そしてもちろんここに答えはなく、だからその論理を自分で構築していく必要が出てくる。
それが分からないからどう生きていけばいいか分からないということなる、
つまりどう生きるかどう振舞うかの前に、「人生というものをどう捉えているのか」が先にあって、そしてそれをそもそも捉える論理を持ち合わせていないことが根本的な問題。
で、その一つのモデルとして「人生の軸」という話をしていて、でもそれはあくまでも入り口でしかなくて、
方向性は分かったとしても結局は日々その方針に沿いつつ進んでいくわけで、そのときにはまたその時々の状況を認識できる論理が必要になってくる。
▶練習とか準備とかではなく提出可能な運動の連続としての日々を過ごすという話
いろんな論理を混ぜ合わせていく感覚
ここも実際にはかなりの範囲をカバーできる論理を持っていればそれで大体は対応できる、ということもあるかもしれない、
でもいきなりそんなものがあるなら何の悩みもなく進んでいけるわけで、だから徐々に自分の論理というものを構築していきそれによって目の前の問題に対処していく、
具体的には例えばブログで言えば、
じゃあどうやって取り組むのかと考えるときに、いわゆるブロガーみたいなやり方や今だったらインフルエンサー的やり方というのがあって、強い言葉で注意を引くような形で気づいてもらうというやり方はある。
ただそれがしっくりこない場合には、「質のいいものを淡々と作っていく」というやり方もあり、でもその場合はそもそも見つけてもらえないかもしれない、
そうなると、じゃあそれと並行して知り合いとか今後会う人に喋りまくって口コミで拡散してもらう、ということを考えるかもしれない、
でもこの辺もすべて「ブログというものをどういう論理で捉えるのか」という話になってくる、
▶価値提供するだけの情報発信が破綻する世界で歩みを止めず進み続ける方法
そしてその論理というのは、すでにある誰かが開発した論理を採用するだけで気持ちよく行けるというわけでもない、その場合の方が少ない、
だからそれはまた自分で調整していく必要があり、そうなったときに、例えばめっちゃ適当に言えば宮沢賢治の「農民芸術」という論理がその人にとってはぴったりはまるかもしれない、鶴見俊輔の「限界芸術」という論理がいいかもしれない、ジョンデューイの「経験としての芸術」という論理で捉えることでスムーズにいくかもしれない、
だからあらゆる論理を見ていきながら別の分野に移したり統合したり分割したりしながら、その時々の問題を対処するにふさわしい論理というものを作っていくことになる。
それが学ぶということであり、それ自体も自分の人生を進んでいくということである。
論理群と決断
『知の論理』の最後に、「理論群を統合する大理論があれば、キリスト教的世界観の様に決断ではなく解を出すことができる」という話がある。
つまり、実生活から生まれる論理の欠片、ここでは論理素といってるが、それを集めてきて論理をつくり、それらをいくつか束ねて論理群とする、
その論理群はすべて合体させることはできないが、というかそれをできたとみなす価値観には大いに危うさがり、
だからひとまず実用的なところでは論理群をいっぱい持っていてそれをその時々に合わせて組み替えるという対応の仕方が自然なように思える。
そしてその道中で論理群では解を出すことができない問題が現れ、それはとうぜんで、
どこまでいっても他の論理群との整合性を考えるときには不具合が生じる可能性を常にはらんでいるもので、だからどこまで行っても「決断」にとどまる。
そしてだからこそこの決断の力強さが重要になってきて、その力強さのことをエフィカシーという。
▶エフィカシーが高い人は服を「着れるか」じゃなくて「着たいか」で考える
「日常の仕事の閉じた緻密な論理がより広い世界で矛盾を作るとき、私たちに要求されるのはひとまず、そのレヴェルの論理群の論理を詰めることです。」(『知の論理p315)
「人生の軸」のようなものを必要とするのも、それまで生きてきた文脈や好きな感覚と社会での生活をつなげる論理を持ち合わせていないから。
「こんな感じで生きていきたい」とか「これはしたくない」というのはあるのに、でもその感性を持ちながら社会生活をしていくことは不可能に思えて、
しかもその構造をわかっていないのだから、何をどこからどう手を付けていいか分からないのは当然で、
そこで模索しながら分かってきたことやその中で世界とどう接していくかという論理として考えてきたことがブログの記事になっているわけで、
だから「論理を作り更新していく」という感覚がポイントになってくる、その論理の具体例について考えた。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。