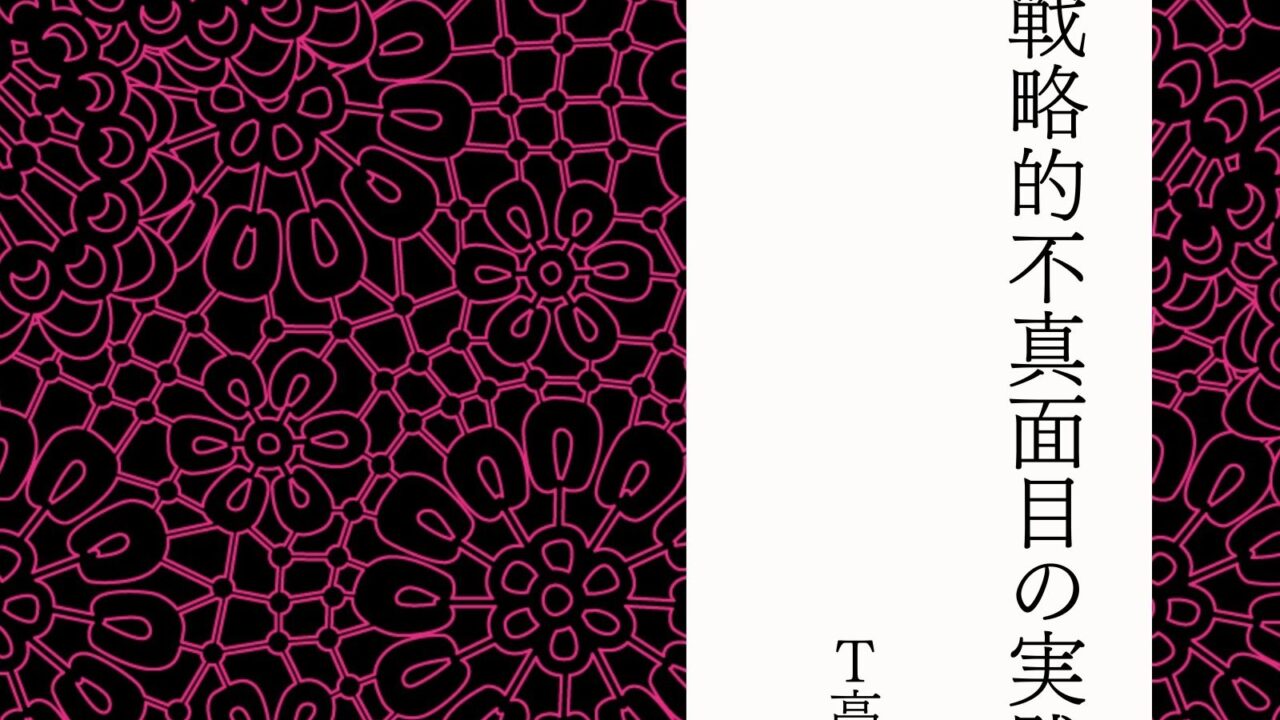電子書籍新しいの書きました。
タイトルは『戦略的不真面目の実践』で、真面目と不真面目についてがテーマです。
このブログにはそういった話をしてる記事が2つほどあるんですが、まとめて読めたほうがよさそうだと思ったので、大幅にアップデートする形で出来上がりました。
▶不真面目な人が得をするのは考えることをサボっていないから。思考停止をやめた話。
▶真面目過ぎる人の努力に対する勘違いと「余裕」とは何か、という話。
といっても、2万5千文字ぐらいなので、記事で言うと8~10個分であっさり読める軽めのやつです。
目次はこんな感じ。
■ はじめに
不真面目になりたい
サボり慣れている人々の特殊能力
■ 真面目過ぎて余裕がない
余裕とは、距離をとること
真面目しか選択肢がないのがまずい
不真面目な自分を登場させて戦ってもらう
不真面目への衝動
■ 真面目と遊びの精神
驚かせてやろうという距離の取り方
別の評価軸で一人のレースを始める
■ 固まった真面目を柔らかくほぐす
与えられた枠を絶対化しない
やりたいことが見つからないときの簡易テクニック
一直線にゴールに向かうのをやめる
■ 真面目と不真面目を統合する
曖昧なままにしておくという不真面目
真面目が活躍するとき
■ 異なる二つの不真面目
どうなってもいいからこれを選びたい
真面目と不真面目の間を調整するのが楽しい
少し内容の話
少し内容の話もしてみると、僕は昔、「自分は真面目過ぎるな」と思ったことがありました。
というよりは、一般的に不真面目とされる人がなんか楽しそうに感じました。
しっかり者ということで結構先生とかには気に入られてきたんですが、「そんなんより適当に遊んでる方がおもろそうやん」と思い始めてきました。
でもそれは確かにその通りで、僕が真面目であると思っているときの真面目というのは、「実直で誠実」というよりは、
もちろんそれも多少はあるかもしれませんが、「今いる環境で正しいと決められていることを逆らわずにその通りにやる」という意味の真面目でした。
つまり、学校ならただ黙って授業を聞いてたくさん発言をしてちゃんと提出物を出していればそれで真面目なのです。
当然先生は喜ぶでしょう。
でも先生をいくら喜ばせても仕方がありません。
自分がそうしたいと思って先生が喜んでくれることをやるのとは話が違います。
手紙を書いたりサプライズの企画してるわけじゃないですからねw
「学校というコミュニティにおけるお行儀の良さ」を身につけているだけなのです。
それで楽しく過ごせている間は何も問題ありませんが、どこかで窮屈に感じることも出てくるかもしれません。
今思い返せば、中学校で遅刻してきたり休みがちだったり、いちいち反抗的な人たちは、言語化こそできてないもののすでにそんな違和感を感じていたのかもしれません。
ちなみに千原ジュニアの『14歳』という本はちょうどそういう話です。
そっから自分の人生の軸的なものとして「お笑い」を見つけるまでの話でおもろいです。
で、そういうお行儀の良さというのは、その環境では重宝されますが、その先何十年と続く個人の生活の心地よさとは、もちろん直結していません。
だからどこかでバッティングするのだと思います。
しない場合は、それは完全に才能なので、そのまま突き進んでいくのでしょう。
この違和感は大学一年生の時に来ました。
そして不真面目な同期にどこか魅力を感じました。
それからちょっと不真面目さが必要かもしれないと考え始めたのですが、その2,3年の出来事をベースに、
「本来真面目な僕たちが、自分なりのちょうどいい不真面目さを見つけていくには」
という内容です。
といっても、そんなにかっちりした話では全くないので、気楽に読んでもらえたらと思います。
ブログの記事だと自分の話を長々としてられないので、複数回分を束ねて本したという感じでしょうか。
あとさっき、「適当に遊んでる方がおもしろそうやん」と流れで言ってしまいましたが、本当はそれも違っていて、適当ではなくちゃんと遊ぶ方がおもしろいです。
というわけで、今回で僕の中で「不真面目論」というと大げさですがw、その辺りについては一段落ついたので非常にすっきりしてます。
amazonのページで無料サンプルもゲットできるので、興味あらばぜひ読んでみてください。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。