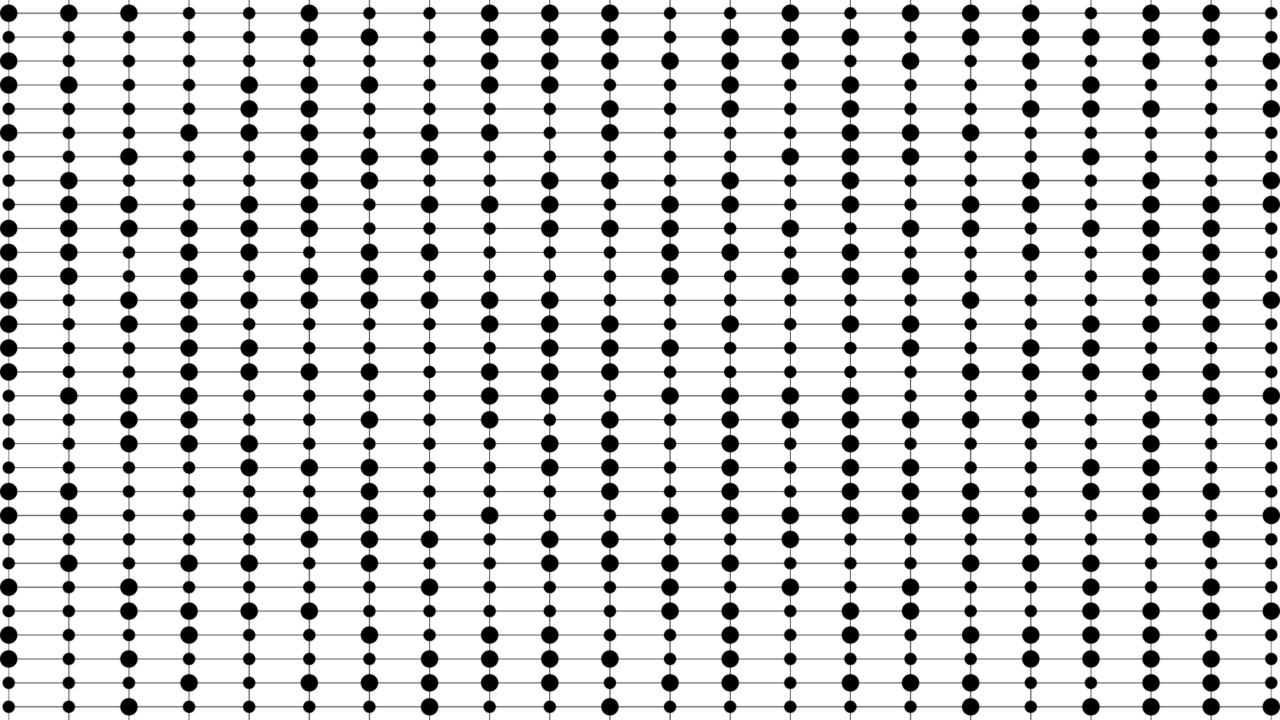こんにちは、高本です。
今回は、いろんな学問の境界を溶かしてつなげて考えていくと面白い、という話。
ジョブズが言った有名な言葉でコネクティングドッツってありますよね。
あれはいろんなことに取り組んで没頭していれば、あとからそれらがつながっていくよという意味でした。
これはブリコラージュ的な発想ですよね。
とりあえずなんか使えそうだから集めておいて、何か作りたいものとか目指したいものが立ち現れてきたときに、その自分の周りのありあわせの道具と素材で何とか形にしていく。そういう考え方。
だからその時に使える手持ちの道具が多いほうがいいわけで、でもないならないなりに何とか完成系に近づけていくという発想ですよね。
だから日常としては、その道具や素材が増える方向に動いて経験していくのがいいと思うんですが、まあそれはいいとして、学問においてもこの感覚で捉えておくと面白くて。
数学と音楽と物理と道教
そもそもまず文系と理系っていう区分けがあるわけですけど、こういうのはあんまり考えない方がいいと思っていて。
むしろ全部繋げるつもりで、というかつながってるつもりで学んでいくほうが圧倒的に面白くて。そもそも学問は哲学から始まりますけど、そこで宇宙とか物質の構成要素とか考えてたものが物理に分かれていき、神を考えてたものが神学になっていくわけですよね。
だからおおもとに立ち返れば、この世界の成り立ちとか人間がどういう生き物かって考えてたところが始まりで。
であればそれぞれを別物としてその領域だけでやっててもつまらないし、もっと枠を広げて全部統合して考えたほうが見えてくるものもあるし、その方が世界を面白く見れる。
例えば音楽と数学はつながってる部分ががあって。音階は周波数で定義できるから、こうなると物理も関係してきますけど。ニュートンは1600年代に偉大な物理の本を書きました。
ニュートンと錬金術

まずは高校で物理をやるときはその世界観で学んでいくんですけど、でもニュートンは神が作ったこの宇宙は完璧に調和してて、数式で完全に記述できるはずだって信念を持っていました。
で、それに取り組んだ結果としてニュートン力学ができあがるんですよね。
この本はプリンキピアって言うんですけど、直訳すると『自然哲学の数学的諸原理』で、だから自然哲学なんですよね。ニュートン自身が自分でやってると思ってたことは。
晩年は錬金術にはまっていくんですけど、これも神が作ったこの世界を解き明かしたい、その法則を解き明かしたいっていうのがあるわけです。
じゃあ物理と錬金術のつながりとか、そもそも錬金術も胡散臭いって感じありますけど、それも神が作った世界に到達する営みだったりして。
じゃあ神学とも結びついてくるし、当時の人間の宇宙観とも結びついてきて。
現代物理と東洋思想
しかも現代では宇宙は物理の言語で記述できるわけで、そもそもその現代物理は東洋思想と関連してるかもって話もあって。
例えば道教の老子で言えば「道(タオ)」っていう母なる大地があって、そこですべてのものが生まれてくるし、そこに消えていく。
そんな場所みたいに言われてますけど、物理では”真空”って概念があって、そこで粒子が無限に生成と消滅を繰り返す。だからこれは一緒のこと言ってるんじゃないかとか。
異なるリズムの世界をつなげる
あとは数学と音楽の話に戻ると、リズムの刻み方も数学で考えられますよね。
例えば2拍3連のリズムはタン、タンの2拍の中に音符が3つですけど、2の世界と3の世界の融合であり統合である、みたいに考えることができて、異なる世界をつないでいくっていうある種コネクティングドッツですよね。
それって2でも3でもない新しい世界なわけで、じゃあそのリズムの中で何かメロディーを考えるとすれば、それはその音楽宇宙で遊ぶってことなわけで。
で、アインシュタインがバイオリンやってた話は有名ですけど、物理学者のヘルムホルツも音楽の本を書いてたりすんですよね。
じゃあ例えば心地いい音楽を考えてみると、これはまたちょっと前に紹介した1/fゆらぎが出てくることになって。
じゃあその音楽を解析するってなると、これは波をフーリエ変換使って分解するわけで、これは物理とか数学の領域。
1/f ゆらぎ

じゃあなんで1/fゆらぎが心地いいのかって言うと、人間のリズムも1/fでゆらいでいて、例えば人がリラックスしてるときはα波の脳波ですけど、これがそもそも1/fゆらぎと呼ばれるものだったりして。
だからこのゆらぎのものに触れるときに、人は心地いいと感じるんじゃないかって話で。
じゃあそもそもなんで1/fゆらぎになってるのかって言えば、自然界は波とか川とかそのゆらぎ方のものが多くて、そんな地球そんな宇宙のリズムの中で進化を繰り返してきたから、人間もその環境の影響を受けてるはずやんという話で。
ってなれば数学と音楽の話からだいぶ広い領域に拡大していくというかつながってくるというか。
その音楽とか数学も逆にもっと遡っていけば哲学にくっつくわけで、じゃあその哲学はって言うと、「人間とは何か」とかを考えてたわけだから、じゃあもう全部一つですやんということでもあってw
音楽的世界観

そうするとじゃあ音楽を考えるとか楽器をやるとなったときに、好きなアーティストの歌をコピーするのもおもろいけど、
そもそも音楽とは何なのかって観点から、ここまで見てきたものにつなげて考えていくこともできるし、
人が感動するような演奏をしたいと思えば、じゃあ1/fゆらぎっていうのを頭に置いたうえで、曲を作ることもできるかもしれないし、
新しい音楽を作りたいとなれば、数学的に考えて元々あった2つのリズムの世界を融合して、その新しい世界に昔あったメロディーを持ってきたらどうなるんやろうとか考えることもできるわけで。
さらに言うと、その音楽的な発想を絵に落とし込んでみたらどうなるかなとか考えても面白くて。
喋りのリズムと音楽と変性意識
で、言い忘れてたんですけど、音楽で言えば、例えばスピーチとか落語とかも音楽的に考えられるはずで。
あれって上手な人とか聞き入ってしまう人ってのは、たぶん音楽的に見たときに何か特徴的なことがあるはずで。
だっていい音楽を聴いてるときってなんかちょっと別世界に意識が飛ぶようなうっとりするような感覚があって、途中で現実に急に引き戻されたりってことはなかなかなくて。
じゃあスピーチとか演説にしても、そのリズムとか抑揚を音楽として考えてみたりもできるはずで、歌舞伎とか能とか漫才とかすべらない話ですらたぶん何かちょうどいいリズムと抑揚になってるはずで。
で、もっと言えばそのうっとりする感覚は、これは変性意識とかトランス状態って言うわけですけど、音楽はこれの導入によくて。
例えば昔の部族とかは狩りに行く前、気持ちを高ぶらせるために音楽とか舞踊みたいなものを使いますよね。
道路横に急に現れるコロンビア先住民、エンベラチャミ族の居住区にお邪魔【南米旅行記③】
南米とかではシャーマンが儀式するときに音楽を使って、それによって神が現れてくる感覚になるとか、神秘的な体験をするとか。
 アマゾンで部族の暮らしを体験した時のやつ。一番左のおっちゃんが長老的な人でコミュニティの伝統的な歌を歌ってくれました。
アマゾンで部族の暮らしを体験した時のやつ。一番左のおっちゃんが長老的な人でコミュニティの伝統的な歌を歌ってくれました。じゃあ儀式ってそもそも何なのかみたいなところまで考えると、これは宗教的な活動で、そうするとキリスト教とかにもつながってくるし。
そもそもなんで人間は宗教というものを作り出したのか、それを欲するのか、人にとって宗教とは何なのか、とかにもなってくるし。
まあ結局全部つながってると思えば、どっからでも世界を面白がれるようになってきますよねって話ですよね。
適当にバラエティ番組見てても言語とか聴覚とか音楽とかの観点からスタートして、じゃあその結果今の自分の生活とか行動に落とし込むならどうなるかってまた戻してくれば、何をしてても面白くなってくるし何をしててもパワーアップ出来てくるかもしれないし、それは自分が向かっていきたい方向に進んでいくことかもしれないし、という話ですね。
しかもその変性意識って言葉が入ってきやすいとか、潜在意識を書き換えやすい状態って言われていて。
だからコピーライティングでは五感を刺激するような表現を使えとか、動きを表す言葉を使えとか、頭で想像できるような表現を使えってありますけど、頭で想像するってことはそっちの世界に臨場感を持つってことで、これがまさに変性意識状態なわけですよね。
だからそうなるとこっちのメッセージが届きやすいってことか、とか、そもそもヒトラーの演説も聴衆が変性意識に入りやすいような喋り方とか身振り手振りをできてたからこそ、あれだけの人を動かせてたんじゃないかとか思いますよね。
まとめ
そう考えていくと文型とか理系とか分けて考えてるのあほらしいというかアートとサイエンスをいい感じに融合させるというか、そういう方がおもろい感じの見え方はできてきますよね。
ちなみにトランスに入る作法がしっかりあるのは、ヨガとか仏教とかですよね。
さらに言えばこのトランスは没頭するってことにも関わっていて、それがチクセントミハイって人のフローっていう概念で、忘我の極致というかスポーツ選手のゾーンとかの話。
で、”遊び”もこの感覚と関わってて、だからそういう意味でも遊びが大事になってくるんですけども。
今回は以上です。ここまでお読みいただきありがとうございました。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の補足音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。