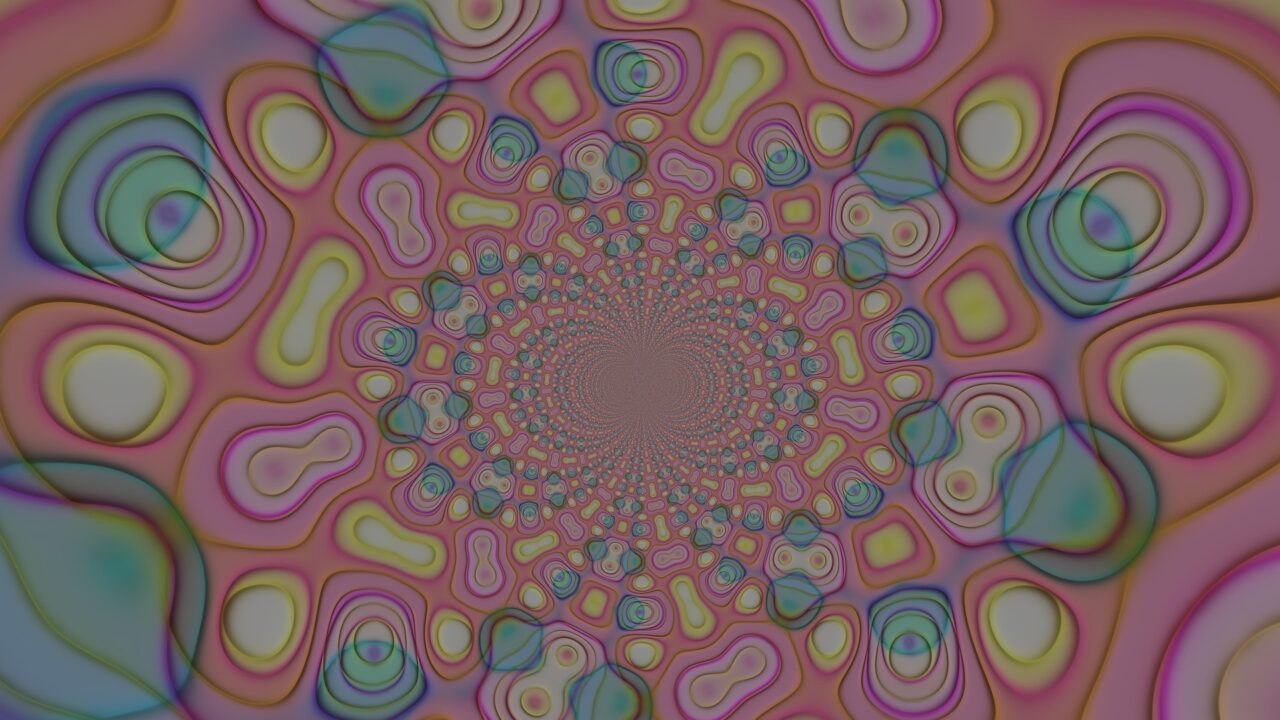たまたま見返した昔のメモでちょっと思ったことがありまして。
24/6/30
目が覚めたらつけっぱなしのイヤホンから「有田脳」というラジオが流れてた。「今はニュースターがいないって話してた。
今は関心が分散するから、昔みたいにマスメディアでテレビと新聞でずっと国民に訴えかけたりしないから、その分野でのスターに限られる。
朝空港で2,30人の人だかりができてたけど、出てきたのは知らない人で近くにいた人に聞いてみたら、「パチンコ会のキング」って言われて、「でも知らんな」って言ってたけど、そういう時代なんだと思う。
逆にその朝の空港に2,30人集まるのその規模で熱狂的なファンがいたら成立する時代、それだけでもう生きていける時代。
まさに八百万の神を目指す時代。
結局その分野ではどんだけ有名でスターでも、興味ない人からすれば全然知らない人、ユーチューバーでもお笑い界でもプロレス界でも野球界でも、その界隈の人は全員知ってるスターでも隣の分野に行けば誰も知らない。
じゃあそんな時代に何をすればいいのかというと、自分で範囲を区切ってまずはその閉じた空間で自分を確立する。そういう情報発信ってことになる。
そもそも区別するって発想がもうすでに変なんじゃないんか。
『タオ自然学』の最初のほうで、「昔の人は科学と宗教と哲学を区別しなかった」とか「生物と無生物を区別しなかった」「それより真の追求をしようとした」って話あるけど、その通りで、
だって本来自然は自然としてあるのみで分かれてない。
こっちが勝手に捉えどころのない自然を手元に置いときたいがために、分けて別のものとして区別してる。
近代になるにつれて分けて考えていくようになってるだけ、
医学でも中国の気は体全体の流れから考えていくのに対して西洋のは部分的に治療するけど、
それも全体を考えるの無理だから部分ごとに見ていってるだけで、本来は人間の体は一つのもので、なんやったらそれも宇宙という全体の一部に過ぎない。
(メモ終わり)
外に答えを見つけに行くのではない
というメモがあったんですが、これ今西錦司の「自然学」の発想にかなり近い。
最近この「全体のまま受け取る感覚」が出てくる本が多く、それは本から吸収したというより、やっぱり自分の中に元々あった気質のようなものがでかい。
それ自体も結局は何かに触れる中でその感覚になっていくという意味では影響されているかもしれないが、その本に染まっていくのとはまた違っていて、
外部との相互作用の中で自分の感覚の暫定版のようなものが確立されていき、それがまた外部の何かと共鳴することで、
いや、外部の存在という振動物に触れ、それと共鳴した時に、初めて自分もその振動数を持っていたことに気づく、
そう、だから、440hzで振動するラの音叉に近づいたり触ったりしたから自分が440hzになるのではなく、その音叉と共振したことから自分の振動数も440hzだったことに気づく、というイメージ、
もしくはきれいに響きあう、ドとかミかもしれない、でも不協和音ではなく、自分が今それに触れたときに、内側の感覚のところで不快さを感じなかったという事実が、その振動数的気質を持っていることの証明となる。
外との接触はそれを確かめていく時間ともいえる。
▶やっぱり人生の軸も日常も子供の時の感動をベースに考えていくのがよさそうという話
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。