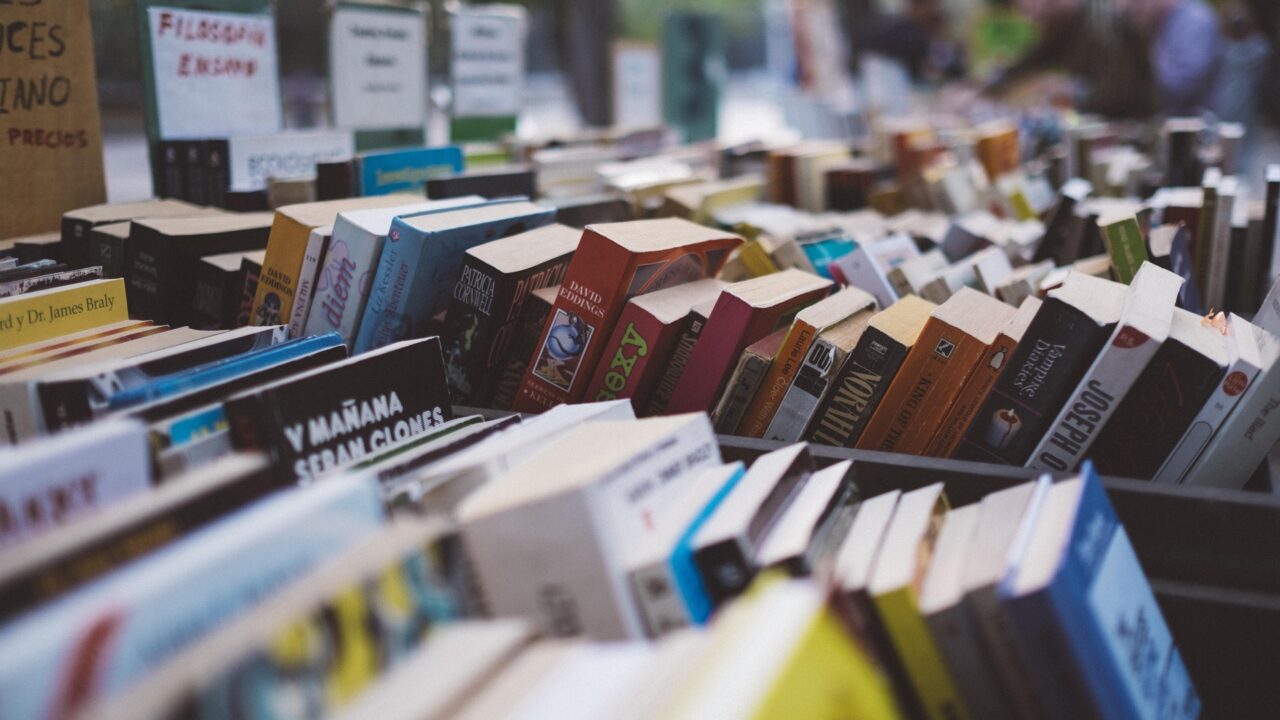最近エネルギーと人類の関わりの歴史を見ていた。
その中でエネルギー源として石炭が使われるようになる経緯が出てくるのだが、ぱっと浮かぶのは産業革命で、これによって木炭から石炭に移行していく。
もともとはエネルギーや富の源泉と言えば土地で、地代として徴収したり農作業によって太陽エネルギーを生産物に変換して取り出していた。
森林では木を伐採し、薪として暖炉に使われたり建築に使われたりした。
そういう意味で木とその源である土地が価値あるものとされた。木によるエネルギーとして木炭が多く使われた。
そこから蒸気機関などに見られるように、石炭を動力源とする時代に移り変わっていく。
そんな石炭についてみていると、「産業革命や蒸気機関以降使われるようになったと思われているが、石炭は元々製鉄の分野で使われていた」という記述がよく出てくる。
化学は全然分からないので細かい説明はできないが、要は鉄を得るには酸化鉄から酸素を取り除く必要がある、これに木炭を使っていた。
つまり、2FeO + C → 2Fe + CO2 みたいな式になる。
と思ったが検索して確かめてみると、現実的には Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO2 という式になるようでこれは見覚えがある。
これが木炭の代わりに石炭を使う製鉄の方法で、石炭は不純物が多く使い勝手が悪いのでそれらを取り除いたコークスを使う。
見覚えがあると書いたのは、高校の化学で製鉄のいくつかの段階ごとに反応式と得られる鉄の量などをめっちゃ計算させられた記憶があり、その時は「何やねんこの問題」と思っていたが、
で、ここからが今回の本題なのだが、当時は何やねんと思っていたものが、今になって振り返ってみると歴史的に重要な発明や転換点をベースにした問題であることが多い。
これももちろんその一つで、もともとは木炭を使っていたが、森林を伐採しまくって気が枯渇してきたタイミングで石炭が使われるようになり、
でも不純物の含まれた石炭からでは良質の鉄は得られず、だからそれを取り除きコークスという形で利用するようになっていく。
そしてこのときの高炉などの設備のイラストが教科書などにも出てきていた。
他にもハーバーボッシュ法という「空気からパンを作る方法」と言われる発明があり、空気中の窒素と水中の水素からアンモニアを作る方法である。
これが肥料の原料となるので空気からパンが作れるというわけである。
ということも高校生の時はもちろん知らないが、これまた化学の計算問題として非常によく出てくる。
こういった鉄やアンモニアを作る方法はそういった分野に進めば大前提になってくるのだろが、それらをしれーっと教科書に忍び込ませてくれているというわけである。
で、その道に進まずともこれらは普段使う身の回りの物やその原料がどのように作られているのか、そしてそれがどれだけ偉大なことなのか、授業内でその背景まですべて扱うことはできないにしても、
また数年後にでもどこかのタイミングで「なんか聞いたことあるな」って思えるように前振りとして種をまいててくれていたのだ。
高校物理では原子の単元で「光電効果」という金属に光を当てると電子が出たり電流が流れる現象を扱い、またその計算などもするが、
これはアインシュタインが4つの論文で次々に物理の基本的概念の理解を大きく進めた「奇跡の年」とよばれる一年の初めに出した論文で扱われたものである。
というわけで、僕たちはアホみたいな顔して適当に横流ししているが、実は教科書で取り上げられる話題は相当に考えられている。
多分その科目ごとに本当に重要な出来事や各時代の転換点となるようなトピックから問題が作られている。
自分の興味のもとに真の勉強を始めなければそれに気づくことはない。
現在、やりたいことや没頭できることがなく、でも何からやればいいかわからないという、人生と向き合い中な方向けに
●客観的な幸せや豊かさではなく、自分のコアや方向性を見定める
●ゼロヒャクのおもんなくそ真面目二項対立思考を手放す
●内から湧き上がる好奇心や心躍る感を汲み取る感覚を取り戻す
●自分を起点に盛大な循環を巻き起こす手段として情報発信を捉える
などのテーマを中心としたメルマガを配信しています。
「想定外連発で予定不調和のおもろい人生に突入したい」
「理想の未来とつながった今日一日を日々過ごしていたい」
という、まじめにふまじめに自分なりの人生を追求する愉快な人たちが集まるメルマガコミュニティです。
登録直後にお届けする、「人生の方向性(自分軸)の見定め方」を解説した23ページのレポートとワークシート、合計50分の追加音声で、
まずは明日からの次の一歩の方向を仮設定してみてください。